生活保護受給者の遺品整理は誰がやる?相続人の義務と補助の有無を紹介します
投稿日:
更新日:
- 遺品整理

生活保護受給者が亡くなった後の遺品整理は、法的手続きや費用の問題など、多くの課題があります。
「勝手に遺品整理しても良いの?」「役所との連携がわからない」「相続放棄したい」など、ご希望によって対処方法が異なります。
このコラムでは、相続人の方々や関係者の方々が、スムーズに遺品整理を進められるよう、必要な情報を整理してお伝えします。
・生活保護受給者の遺品整理は誰がすべきか
生活保護者が亡くなった場合の遺品整理は、基本的に遺族が実施します。しかし、身寄りがない方や相続人全員が相続放棄をするようなケースでは、相続人以外によって遺品整理をしなければならないケースもあります。
・生活保護者の遺品整理費用は相続人の負担になること
基本的に生活保護の方の遺品整理費用は、相続人が負担します。生活保護なので役所が負担してくれると思いがちですが、それはあくまで生きている間のみ。亡くなった時点で支援が打ち切られてしまいます。
・生活保護者が亡くなった際に利用できる葬祭扶助について
生活保護の方が亡くなった場合は、葬儀費用を補助してくれる制度が利用できます。遺品整理の費用に加えて葬儀費用もとなると出費が大きくなるので、利用できる補助制度は活用すべきです。
・費用を抑えて遺品整理をするためのコツ
遺品整理の費用を抑えるためにできることを、遺品整理業者の目線からお伝えします。なるべく出費を抑えて故人を弔うための方法になっているので、ぜひ活用してください。
いますぐ遺品整理業者をお探しの方へ
遠方からでも大歓迎!
遺品整理、生前整理ならお任せください。
すぐに駆けつけます!
- 365日年中無休で対応
- 最短30分で駆けつけ見積もり
- 鍵預かり、遠方対応可能
- ご見積もり後のキャンセル無料
目次
生活保護受給者の遺品整理は誰がやるのか

生活保護を受給していた方が亡くなった場合、その遺品整理をどのように進めるべきか、多くの方が不安を感じています。このコラムでは、生活保護受給者の遺品整理に関する基本的な考え方から実務的な対応まで、法令に基づいて解説していきます。
遺品整理は相続人の義務
遺品整理は、原則として相続人が行う必要があります。これは民法第896条および第897条に基づく相続の基本原則によるものです。
(相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
引用:法令検索
生活保護受給者であった場合でも、この原則は変わりません。相続人は被相続人の権利義務を承継する立場として、遺品の整理についても責任を負うことになります。
相続人以外が行うケース
相続人による遺品整理が困難な場合も少なくありません。そのような場合には、法令に基づいて相続人以外が遺品整理を行うことになります。
まず、相続人が存在しない場合には、民法第951条の規定により、相続財産は法人として扱われます。
(相続財産法人の成立)
第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
引用:法令検索
この場合は家庭裁判所が選任した相続財産清算人が、相続財産の管理・清算を行うことになります。
少しわかりにくいのですが、亡くなった方に相続人がいない場合は、その遺産が宙に浮いてしまい、処分ができません。
そこで救済措置として遺産自体を法人扱いにして処分する、というのがこの法律の考え方になっています。
身寄りのない生活保護受給者が亡くなった場合、その死亡地の市町村が必要な対応を行います。具体的には、墓地埋葬等に関する法律(墓埋法)第9条、または行旅病人及行旅死亡人取扱法(行旅法)第7条に基づいて、遺体の火葬や遺留品の管理などの措置が取られます。
つまり一時的に市町村で遺体の火葬や遺留品の管理をして、本当に相続人がいないかを調査するという流れです。
また、福祉事務所が死後の事務管理として関与するケースもあります。特に、相続人の有無が不明な場合や、相続人との連絡が取れない場合には、福祉事務所が一時的に遺品の管理を実施します。
相続人以外が遺品整理を行うケースについてはこちらの記事で紹介しています。
相続人が遺品整理を避ける方法
相続人にとって「遺品整理の負担が大きすぎる」「そもそも故人と関係が悪かったので、遺品整理をしたくない」というようなケースもあるはず。そのような場合には、相続人が遺品整理をしなくて済む方法を取ると良いでしょう。
まず有名なのが「相続放棄」です。相続人は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申述をすることができます。
相続放棄が認められると、その相続人は最初から相続人とならなかったものとみなされ、遺品整理の義務を負わなくなります。ただしいったん相続放棄をすると取り消すことはできませんので、慎重に判断しましょう。
また、限定承認という方法もあります。これは、相続によって得る財産の限度においてのみ被相続人の債務を弁済する責任を負うという制度です。つまり相続する財産がなければ、予期せぬ債務の負担を避けたい場合には、この限定承認を選択するのがおすすめです。
限定承認も家庭裁判所への申述が必要となりますが、相続財産の範囲内で責任を限定できるため、必要以上の負担を負わずに済みます。
単純に遺品整理の労力が大きいと感じる方、または遠方で遺品整理が難しい方は、専門の遺品整理業者に依頼することも可能です。
この場合責任は相続人にありますが、実際の整理作業は専門家に任せることができるので、負担はかなり軽くできるはずです。
生活保護者の遺品整理費用は相続人が負担する

生活保護受給者が亡くなった場合でも、遺品整理にかかる費用は原則として相続人が負担することになります。これは相続人が被相続人の権利義務を包括的に承継するという民法の基本原則に基づく考え方です。
しかし生活保護受給者の場合、遺産がほとんどないケースも多いため遺産から払えないケースも非常に多いです。遺品整理の費用の負担をどうするかは、慎重に検討した方が良いでしょう。
生活保護費を遺品整理に充てられない
生活保護法の原則として、生活保護費を遺品整理の費用に充てることはできません。生活保護費は、あくまでも受給者本人の最低限度の生活を保障するために支給されるものであり、死後の遺品整理費用は想定されていないからです。
ただし、葬祭費用については、生活保護法第18条に基づく葬祭扶助の制度があります。厚生労働省が発表した令和6年度の葬祭扶助基準によると、1級地および2級地では215,000円以内、3級地では188,100円以内が支給されます。
この葬祭扶助は、火葬や納骨などの葬祭に直接関係する費用に充てることができますが、遺品整理の費用は対象外となります。
なお、葬祭に要する費用が基準額を超える場合で葬祭地の市町村条例に定める火葬費用が一定額を超えるときは、その超過分について加算措置があります。また、遺体の運搬に要する費用についても、一定の条件下で加算が認められています。
遺留金品の取り扱いについて
生活保護受給者が亡くなった際に残された遺留金品については、厚生労働省が定める「身寄りのない方が亡くなられた場合の遺留金等の取扱いの手引」に基づいて処理されます。遺留金品はまず葬祭費用に充当され、余りが生じた場合には相続財産として扱われます。
「市町村は遺留金品を葬祭費用に充当することができる」とする生活保護法第76条第1項の規定により、相続人に優先して遺留金を葬祭費用に充当することが可能です。
また、預貯金が残されている場合、その引き出しについても相続人への意思確認は不要とされています。
このように、遺品整理の費用負担は原則として相続人にありますが、実際の対応においては、遺留金品の存在や葬祭扶助の活用など様々な要素を検討した上で負担するか決めると良いでしょう。
役所の方は「相続人がやるように」言ってきますが、実際相続人に秘密の借金があるようなケースもあるので、急いで返事をするのは危険です。
一度検討してから返事をするとし、なるべく早く専門家に相談して相続放棄をするか、自分で負担するかを決めましょう。
生活保護者が亡くなった際の補助について
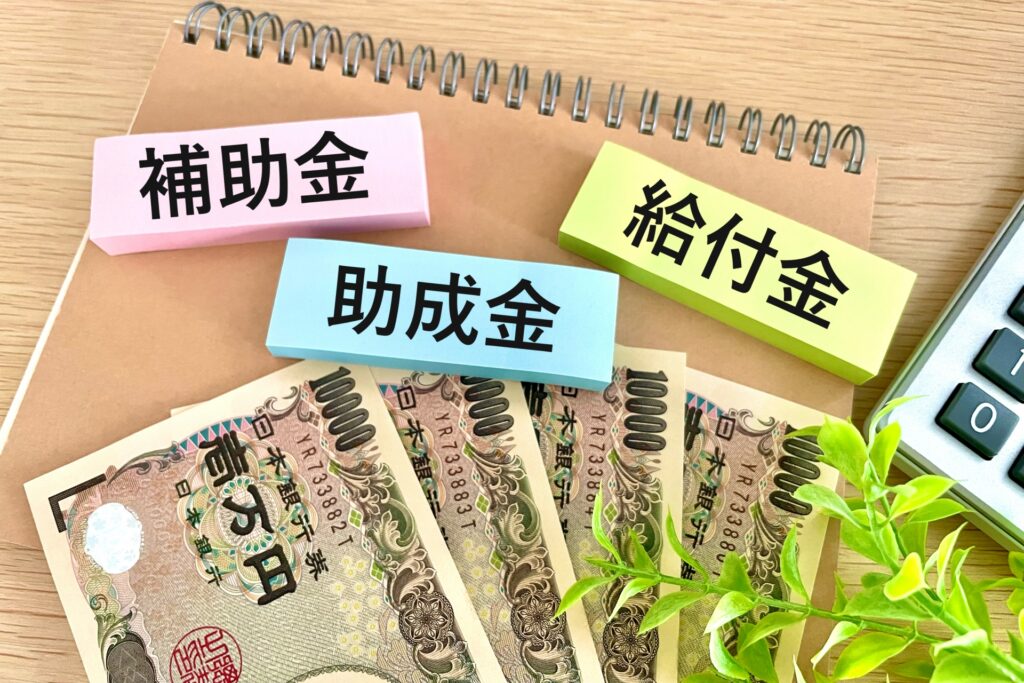
生活保護受給者が亡くなった場合、その後の手続きや費用について様々な補助制度が設けられています。これらの制度を適切に活用することで、相続人の負担を軽減することが可能です。ここでは、主要な補助制度について詳しく解説します。
葬祭扶助の申請
生活保護法に基づく葬祭扶助は、経済的に困窮している世帯に対して設けられた重要な支援制度です。この制度は故人の尊厳を守りながら、葬儀を執り行うことができることを目的として作られました。
葬祭扶助は、令和6年度の基準では、1級地および2級地において大人215,000円以内、小人172,000円以内が支給されます。3級地においては、大人188,100円以内、小人150,500円以内となっています。
これらの金額は、地域の実情に応じて設定されており、葬祭に必要な基本的な費用をカバーすることを目的としています。
さらに、自治体の条例で定める火葬費用が一定額を超える場合には、追加の加算措置が設けられています。1級地および2級地では大人600円、小人500円、3級地では大人480円、小人400円を超える部分について加算されます。
ここで出てくる「1級2級」というのは、物価などを考慮した地域の区分です。
お住まいの地域が何級に当たるかは、自治体等に確認してくださいね。
葬祭扶助を利用するための条件として、以下のいずれかに該当する必要がある点に注意してください。
- 遺族が生活保護を受けているなど、経済的に困窮している場合
- 身寄りのない生活保護受給者が亡くなった場合
これらの条件に該当する場合担当は、ケースワーカーや民生委員に相談することで、具体的な申請手続きを進められます。
粗大ごみ手数料の減免措置の扱い
多くの自治体では、生活保護受給者に対して粗大ごみ手数料の減免制度を設けていますが、受給者の死後はこの制度が適用されません。
これは、減免措置があくまでも生活保護を受けている本人に向けての制度だからです。受給者が亡くなった場合は対象者が存在しないことになるため、遺品の処分に関しては通常の手数料が発生することになります。
このため、遺族が遺品を処分する際には粗大ゴミ処理手数料を支払う必要がある点に注意しましょう。家財が多い場合は粗大ゴミの処理だけで数万円かかるケースもあるので、費用を抑える対策も覚えておいてください。
可能な限り家具などは分解して細かくし、普通ゴミとして捨てると粗大ゴミの処理費用がかかりません。
なお、自治体によって粗大ゴミに該当する条件、処理料金は変わりますので、事前に自治体に確認してから捨てるようにしてください。
費用を抑えて賢く進める遺品整理のコツ
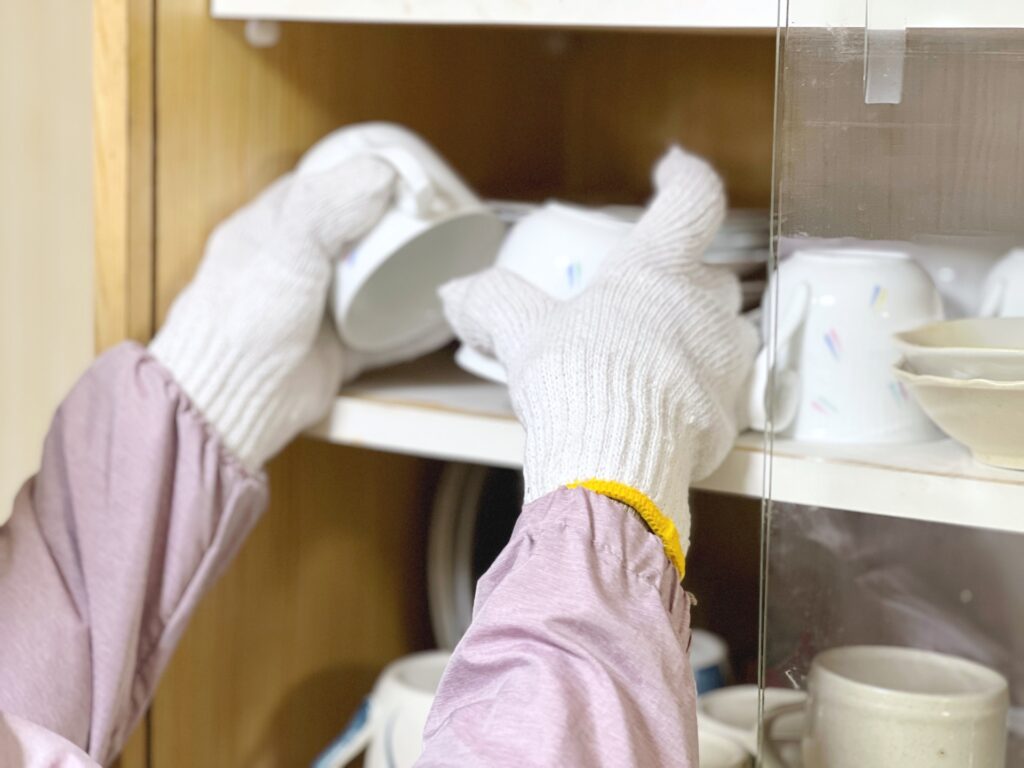
生活保護受給者の遺品整理では、費用を抑えながら効率的に作業を進めることが重要です。ここでは、遺品整理業者の観点から費用対策と作業効率化のポイントについて解説します。
業者に依頼する場合は複数社の相見積もりを取る
遺品整理業者に依頼する場合、費用は業者によって大きく異なるケースが多いです。遺品整理に定価は存在しないので、それぞれ業者が価格設定を決めています。
もちろん相場はあるのですが、それでも数千円〜数万円の違いが出ることはよくあります。
そのため、必ず複数の業者から見積もりを取りましょう。見積もりを比較する際は、単に価格だけでなく作業の明確さや見積りの明瞭さなどに注意してください。
まずホームページや見積書に作業の内容を明確に書いているかどうか、これが大切です。悪質な業者は作業をごまして後で追加費用を発生するという手口を取ります。このために、悪質な業者は事前に作業内容を明らかにしたがりません。
つまり、作業内容が明確などうかを事前に確かめておけば、悪質な業者に引っかかってしまうリスクはかなり下がります。
さらに、業者の信頼性も重要な判断基準となります。営業年数、過去の実績、必要な許認可の有無などを確認し、安心して依頼できる業者を選んでください。
業者には現地見積もりをしてもらう
遺品の量や状態は、実際に現場を確認しないと正確な判断が困難です。LINEなどでの見積もりも可能ですが、あくまで簡易的な見積もりしか出せないからです。そのため必ず現地での見積もりを依頼しましょう。
遺品整理の費用が嵩む原因として多いのは、搬出経路がないことです。家財の運び出しに階段を使う必要がある場合(エレベーターが狭い)などは、人員が必要になるので費用は高くなってしまいます。
また、駐車場が近くになく台車での運搬が必要な場合なども費用が追加されてしまいます。このように追加費用が発生する事例は意外と多いので、必ず現地で見積もりを取って正確な金額を出してもらいましょう。
もう1つのポイントとして、遺品の中に特別な処分方法が必要なものがないかも確認します。家電製品、危険物、貴重品などは、通常の廃棄物とは異なる取り扱いが必要となる場合があるからです。
もしも依頼した業者で引き取れないものがあった場合、他の業者を頼まなければならないので二度手間になります。引き取りできないものがないか見る意味でも、現地調査は重要です。
業者に見積もりを取る場合の相場や取り方について詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
自分でやれるところはやっておこう
遺品整理の費用を抑えるために、自力でできる範囲の片付けは済ませておくと良いでしょう。遺品整理の費用は作業人員とかかる時間が短いほど安くなります。
そのため、できる範囲で事前準備を行うことで、業者への依頼費用を抑えることができます。
例えば、故人が残した書類の仕分け作業などは自分たちで行いましょう。紙は軽いですし、捨てる際も燃えるゴミに捨てられるのでさほど負担はないはずです。重要書類を事前に分類しておくことで、その後の相続手続きもスムーズに進みます。
また、小物類の整理や仕分けをしておく方法もおすすめです。残したいものを事前に仕分けておけば業者の手間を省くことができ、費用も安く抑えられます。
自分で遺品整理を進める方法についてはこちらの記事で紹介しています。
買取店・リサイクルショップ・フリマアプリ等を活用する
遺品整理の費用を抑えるために、遺品の中から売却するものを探すのも良いでしょう。遺品の中にはまだ十分に使用可能なもの、売れるものが含まれているかもしれません。
そのようなものを売却して現金化すれば、遺品整理の費用に充当して負担を抑えられます。
生活保護だから価値のあるものなんてないと思いがちですが、意外と価値のあるものを持っている方は多いんです!
特にコレクション癖がある方は、レトロな価値があるものを持っていたりします。
例として、生活保護の方の部屋にある「売れるもの」は以下のようなものがあります。
- 古銭や切手コレクション
- 大量の小銭
- 古い雑誌コレクション
- コミックの全巻
- 骨董品
なお、一人の判断で勝手に買取に出すと揉め事の原因となるので一度相談し、それから買取に出しましょう。
遺品整理ならしあわせの遺品整理にお任せください

「しあわせの遺品整理」は、生活保護受給者の方の遺品整理において、豊富な実績と専門的なノウハウを持つ遺品整理サービスを提供しています。特にご遺族の経済的な負担に配慮しながら、故人の尊厳を大切にした丁寧な作業を心がけております。
経験豊富なスタッフが、法律や制度を熟知した上で、最適な遺品整理プランをご提案いたします。生活保護受給者の方の遺品整理には、一般的な遺品整理とは異なる専門的な知識や行政との連携が必要となります。
当社のスタッフは、これらの知識を十分につけており、適切な対応が可能です。
ご相談は無料で承っております。まずは、お気軽にお電話やメールでお問い合わせください。ご相談の際には、概算のお見積りをご提示させていただき、作業内容や料金について詳しくご説明いたします。遺品整理に関する不安や疑問点についても、親切丁寧にお答えいたします。
故人との大切な思い出に寄り添いながら、新しい一歩を踏み出すお手伝いをさせていただきます。しあわせの遺品整理が、皆様の心の整理のお役に立てれば幸いです。
遺品整理士の資格を持ち、年間37967件の相談実績をもつ「しあわせの遺品整理」代表。
全国で安心して遺品整理を依頼できる世の中を目指し、人柄・費用・サービス精神を大切に遺品整理業を行っています。
遺品整理士認定番号:IS38071
おすすめの遺品整理業者をお探しの方へ
- 遺品整理
遠方からでも大歓迎!
遺品整理、生前整理ならお任せください。
すぐに駆けつけます!
- 365日年中無休で対応
- 最短30分で駆けつけ見積もり
- 鍵預かり、遠方対応可能
- ご見積もり後のキャンセル無料


