喪中はがきを受け取ったら返事はどうする?4つの対応方法と返事の書き方
投稿日:
更新日:
- その他

「喪中はがきを受け取ったけれど、返事は必要なの?」「どんな対応をすればいいのか分からない…」と悩んでいませんか?喪中はがきは「年賀状を控えます」というお知らせですが、受け取った側としても何かしらの対応をした方がよいのか迷うものです。
失礼のない対応をしたいけれど、どんな返事をすればよいのか分からないという方も多いでしょう。
この記事で以下を中心に解説します。
・喪中はがきを受け取った際の4つの対処方法
何もしなくてもよいですが、喪中見舞いを送る、寒中見舞いを送る、年始状を送ると気持ちを伝えることができます。
・喪中はがきへの返事の文例
「おめでとう」などの言葉を避け、簡潔な文章にするのがポイントです。
・喪中はがきの返事の注意点
遺族の気持ちに寄り添い、使う言葉に配慮しましょう。
この記事では、喪中はがきを受け取った際の4つの対応方法と、失礼のない返事の書き方を詳しく解説します。
様々な状況を想定しながら、それぞれの書き方やマナーについても分かりやすく説明します。
この記事を読むことで、喪中はがきへの適切な対応方法が分かり、相手に失礼のない形で気持ちを伝えられるようになります。
また具体的な文例も紹介するので、どんな言葉を選べばよいのか迷うことがなくなります。大切な方との関係を良好に保つためにも、ぜひ最後までご覧ください
遠方からでも大歓迎!
遺品整理、生前整理ならお任せください。
すぐに駆けつけます!
- 365日年中無休で対応
- 最短30分で駆けつけ見積もり
- 鍵預かり、遠方対応可能
- ご見積もり後のキャンセル無料
目次
喪中はがきへの返事・対応する4つの方法
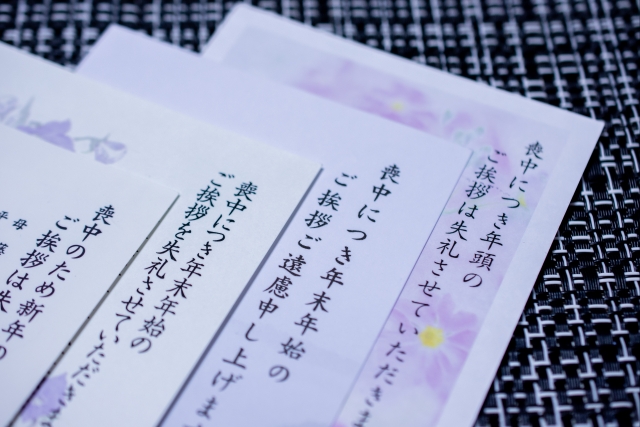
年末が近づくと、「喪中はがき」を受け取る機会が増えます。喪中はがきは「こちらは喪に服しているため、新年の挨拶を控えます」といったお知らせですが、受け取った側としてはどのように対応すればよいか迷う場面も。一般的に、以下の対処方法をとりましょう。
- 何もしない
- 季節の挨拶を兼ねた寒中見舞いを送る
- 喪中見舞いで気持ちを伝える
- 年始状で新年の挨拶(喪が明けた後の配慮)
喪中はがきを受け取った際の対応方法を4つご紹介します。
何もしない
喪中はがきは「年賀状を送らない」といった意思表示であるため、特に何もしなくてもマナー違反にはなりません。
喪中はがきを受け取った相手も、新年の挨拶を控える目的で送っているため、返事を期待しているわけではないのです。
また相手が喪に服している時期は心の整理がついていない場合もあるため、あえて何もせず静かに見守るのも対応としては正解です。
特に親しい間柄でなければ、喪中はがきを受け取ったことを気にしすぎず、自然な対応しましょう。
ただし相手との関係が深い場合は、何もしないと少し冷たい印象を与える可能性もあります。気になる場合は、寒中見舞いや喪中見舞いを送り、気持ちを伝えるのも良いでしょう。
季節の挨拶を兼ねた寒中見舞いを送る
「喪中はがきには返信しなくてもよい」とはいえ、相手を気遣う気持ちを表したい場合は、寒中見舞いを送るのが一般的です。
寒中見舞いは、松の内(1月7日)を過ぎた頃から2月4日頃までに送る季節の挨拶状で、年賀状の代わりとして用いられます。
寒中見舞いの文面には、以下のような内容を含めると良いでしょう。
- 季節の挨拶(「寒さ厳しき折、いかがお過ごしでしょうか」など)
- 相手を気遣う言葉(「ご家族の皆様もお身体を大切にお過ごしください」など)
- 新年の挨拶を控える旨の理解(「喪中とのことで、年始のご挨拶を控えさせていただきました」など)
寒中見舞いを送ることで、「あなたを思っていますよ」「大変な時期でしょうが、お体に気をつけてください」といった気持ちを伝えられます。特に普段から親しくしている相手や、年賀状を毎年交換している相手におすすめの方法です。
喪中見舞いで気持ちを伝える
喪中見舞いとは、喪中はがきを受け取った際に、喪中の方へお悔やみや励ましの気持ちを伝えるためのはがきや手紙を指します。
寒中見舞いが年始の挨拶の代わりになるのに対し、喪中見舞いはより相手の気持ちに寄り添った対応です。
喪中見舞いを送る際は、以下の点に注意しましょう。
- 忌み言葉(重ね言葉や不吉な表現)は避ける(「重ね重ね」「繰り返す」「死」「苦しい」など)
- 簡潔で心のこもったメッセージにする
- あまり形式ばらず、温かみのある言葉を使う
例えば、喪中見舞いの例文には以下があります。
「このたびはご服喪とのこと、謹んでお悔やみ申し上げます。ご心痛いかばかりかと存じますが、ご無理なさらず、ご自愛くださいませ。」
文章は原則として、シンプルな内容が向いています。特に、親しい関係の方には「いつでもお力になりますので、何かあればお知らせください」といった気遣いの言葉を添えるとよいでしょう。
また喪中見舞いとして、お線香やお花を贈るケースもありますが、相手の宗教や習慣によってはふさわしくない場合も。事前に確認しておくと安心です。
年始状で新年の挨拶(喪が明けた後の配慮)
喪が明けた後に、新年の挨拶を兼ねた年始状を送るのもよい方法です。一般的に、喪が明けるのは四十九日や一周忌が過ぎた頃とされますが、喪中の期間は宗教や家庭によって異なります。
相手の状況を考慮しながら、時期を見て送るとよいでしょう。
年始状は、通常の年賀状とは異なり「おめでとうございます」といった表現を避けつつ、新年の挨拶をするのがポイントです。例えば、以下のような文面がよいでしょう。
- 「旧年中は大変お世話になりました。本年も変わらぬご交誼のほど、よろしくお願い申し上げます。」
- 「寒さ厳しき折、いかがお過ごしでしょうか。本年が皆様にとって穏やかな一年となりますようお祈り申し上げます。」
「おめでとう」といった直接的な言葉を使わず、相手を気遣う形で新年の挨拶をするとスムーズです。
また喪が明けたことを確認したうえで、翌年から通常の年賀状を再開するのも良いでしょう。その際、前年に年賀状を控えたことに対する簡単なコメントを添えると、より丁寧な印象を与えます。
関連記事:「身内が亡くなったら葬式後の忌中と喪中でやってはいけないこととは?」
喪中はがきへの返事の文例

喪中はがきを受け取った際、返事をする場合は「寒中見舞い」「喪中見舞い」「年始状」などの形で送るのが一般的です。それぞれの目的や時期に応じた文例を紹介します。
寒中見舞いは、シンプルながらも相手への気遣いを示せるため、親しい人へ送る際に特におすすめです。
寒中見舞いの文例
寒中見舞いは、年賀状を控えた代わりに送る挨拶状で、松の内(1月7日)を過ぎた頃から立春(2月4日頃)までに送ります。
喪中の方への寒中見舞いでは、相手を気遣う言葉を中心にし、「おめでとう」という表現は避けます。
文例1(一般的な寒中見舞い)
厳しい寒さが続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。
先日はご丁寧なご挨拶状を頂き、ありがとうございました。
ご服喪中とのことで、年頭のご挨拶を控えさせていただきましたが、
本年も変わらぬお付き合いのほど、よろしくお願い申し上げます。
まだまだ寒い日が続きますので、お体にお気をつけてお過ごしください。
文例2(親しい方への寒中見舞い)
皆様にとって大変な一年だったことと存じますが、
どうかご無理なさらず、心穏やかにお過ごしくださいませ。
まだ寒さが厳しい時期ですので、ご自愛ください。
喪中見舞いの文例
喪中見舞いは、喪中はがきを受け取った際に、相手を慰める目的で送る挨拶状です。喪中の方が年賀状を控えている時期でも送ることができるため、お悔やみの気持ちを伝えたい場合に向いています。
喪中見舞いは、相手の気持ちを尊重するため、長々と書かずに簡潔にするのがポイントです。
文例1(一般的な喪中見舞い)
〇〇さん(故人)のご冥福をお祈りするとともに、
ご遺族の皆様がどうか少しでも穏やかにお過ごしになれますよう、
心より願っております。
何かお力になれることがございましたら、遠慮なくお知らせください。
年始状の文例
喪中の方が喪が明けた後に、新年の挨拶を控えめに行う場合、年始状を送る方法があります。一般的に喪中が明けるのは四十九日後や一周忌後とされていますが、宗教や家庭によって異なります。
年始状では「おめでとうございます」といった言葉を避け、相手を気遣う内容にすると良いでしょう。
年始状は、相手の喪が明けたことを確認した上で送るのがポイントです。相手がまだ悲しみの中にいる場合は、無理に送らず、適切なタイミングを見計らいましょう。
文例1(一般的な年始状)
旧年中は大変お世話になり、誠にありがとうございました。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
まだ寒い日が続きますので、どうかご自愛くださいませ。
文例2(親しい方への年始状)
旧年中は何かとご心労が多かったことと存じます。
本年が少しでも穏やかな一年となりますよう、心よりお祈り申し上げます。
寒さ厳しき折、どうかご無理をなさらずお過ごしください。
押さえておきたい!喪中はがきへの返事の注意点
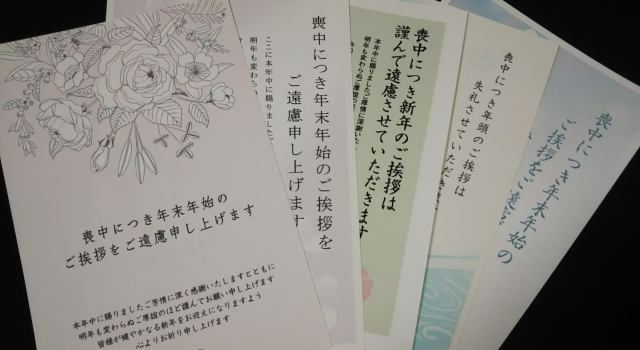
喪中はがきを受け取った際、どのように返事をすればよいのか迷いませんか。基本的に喪中はがきへの返信は必須ではありませんが、相手を思いやる気持ちを伝えるための返事は良い心遣いです。ただし喪中の方への対応には以下の注意点があります。
- 香典は喪中見舞いで(基本が)
- 遺族の気持ちに寄り添う
- メールでの返信は避ける
- 言葉の書き方を配慮しよう
ここでは、喪中はがきへの返事をする際に気を付けたいポイントについて詳しく解説します。
香典は喪中見舞いで(基本が)
喪中はがきを受け取った際に、「香典を送るべきか?」と考えるかもしれません。基本的に喪中はがきは「年賀状を控えます」というお知らせであり、香典を求めるものではありません。そのため香典を送るのは通常の対応ではなく、基本的には必要ありません。
ただし、故人や遺族との関係が深い場合は、「喪中見舞い」として香典やお供えを贈っても問題はありません。喪中見舞いとして適している品物には、以下があります。
- お線香やろうそく(仏教の場合)
- お花(宗教を問わず受け入れられやすい)
- お菓子や果物(家族で分けられるもの)
- 香典(現金)(関係性が深い場合に限る)
贈る場合は「喪中お見舞い」として現金や品物を包み、「このたびのご服喪に際し、心よりお見舞い申し上げます」といったお悔やみの言葉を添えるのが一般的です。
ただし相手の宗教や家庭の方針によっては受け取りを遠慮されるケースもあるため、事前に確認するのが望ましいでしょう。
関連記事:「初七日までしてはいけないこと・食べてはいけないものは?過ごし方まで解説」
遺族の気持ちに寄り添う
喪中はがきを送ってくる方は、大切な家族を亡くしたばかりであり、まだ深い悲しみの中にいるケースが多いです。
そのため返事をする際には、遺族の気持ちを尊重し、思いやりのある言葉を選びましょう。
例えば、寒中見舞いや喪中見舞いを送る場合でも、以下のような配慮ができるとよいです。
- おめでたい表現を避ける(「おめでとう」「祝う」「喜ばしい」など)
- 過度に悲しみを強調しすぎない(「とても悲しいですね」「つらいでしょう」など)
- 遺族の負担にならないようにする(「落ち込まずに頑張ってください」といった励ましは逆効果になることも)
適切な文例としては、以下があります。
「このたびのご服喪の報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。まだご心痛のことと存じますが、どうかご無理をなさらずご自愛くださいませ。」
相手の気持ちに寄り添いながらも、重くならない言葉を選びましょう。
メールでの返信は避ける
近年、連絡手段としてメールやSNSが一般的になりましたが、喪中はがきへの返事をメールで済ませるのは避けたほうがよいとされています。
喪中はがきは正式な挨拶状であるため、返信も丁寧な形をとるのがマナーだからです。
メールやLINEで返信することがNGとされる理由は以下の通りです。
- 形式的に軽い印象を与えてしまう
- 目上の方に対して失礼にあたることがある
- 文字だけでは真心が伝わりにくい
どうしてもメールで伝えなければならない場合は、「お手紙でお伝えするべきところですが、取り急ぎメールにてお悔やみ申し上げます」といった前置きを加えると、失礼のない形になります。できる限り手書きの手紙やはがきで伝えるのが望ましいでしょう。
言葉の書き方を配慮しよう
喪中はがきへの返事を書く際には、言葉遣いにも細心の注意を払う必要があります。特に、忌み言葉や重ね言葉は避けるのが基本です。
避けるべき言葉の例は以下の通りです。
- 忌み言葉(死、亡、苦、四、九 など)
- 重ね言葉(重ね重ね、再び、またまた など)
- 縁起の悪い表現(浮かばれない、終わる、消える など)
例えば、誤った例として「このたびは大変悲しいお知らせを受け、驚いております。ご家族の皆様も辛い日々が続くことと思いますが、どうか乗り越えてください。」といった表現は、遺族にとってプレッシャーになる可能性があります。
代わりに、「このたびはご服喪とのこと、心よりお悔やみ申し上げます。どうかご無理をなさらず、ご自愛ください。」といったシンプルで温かみのある言葉を選ぶようにしましょう。
関連記事:「四十九日とは?意味と葬儀後から四十九日法要前後にすること・準備の方法を解説」
遺品整理のことなら「しあわせの遺品整理」にお任せください

故人が大切にしていた品物を整理することは、残された家族にとって精神的にも肉体的にも大きな負担となるものです。
「しあわせの遺品整理」では、遺族の気持ちに寄り添いながら、遺品整理を丁寧にサポートいたします。
「しあわせの遺品整理」では以下のモットーでお客様に寄り添った作業を行います。
- 専門スタッフが心を込めて対応
- 遺族の希望を最優先に整理を進める
- 供養やリサイクルなど、適切な処理が可能
- 迅速かつ丁寧な作業で安心
遺品整理にはさまざまな悩みがつきものです。「どこから手をつければいいかわからない」「大切なものを適切に処分したい」といったお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。
遺品整理は単なる片付けではなく、故人への想いを整理する大切な時間です。「しあわせの遺品整理」では、想いに寄り添いながら、心を込めてお手伝いさせていただきます。
遺品整理士の資格を持ち、年間37967件の相談実績をもつ「しあわせの遺品整理」代表。
全国で安心して遺品整理を依頼できる世の中を目指し、人柄・費用・サービス精神を大切に遺品整理業を行っています。
遺品整理士認定番号:IS38071
- その他
遠方からでも大歓迎!
遺品整理、生前整理ならお任せください。
すぐに駆けつけます!
- 365日年中無休で対応
- 最短30分で駆けつけ見積もり
- 鍵預かり、遠方対応可能
- ご見積もり後のキャンセル無料


