死亡診断書の発行方法を状況別で紹介!発行の費用・入手できる期限まで解説します
投稿日:
更新日:
- その他

人が亡くなった際、必要な書類のひとつが「死亡診断書」です。死亡診断書は死亡届と合わせて市区町村役場に提出します。
死亡診断書は、さまざまな手続きにおいて提出が必要な書類であり、もし死亡診断書がないとできない手続きもあるため、注意が必要です。
ここでは、死亡診断書とはどういうものか、また発行方法や発行のための費用、入手期限について解説します。
この記事では以下を中心に解説します。
・死亡診断書とは?
・死亡診断書の発行手続き方法と費用
・死亡診断書を提出した後に必要な手続き
・死亡診断書を取得できる条件
死亡診断書と死体検案書、死亡証明書の違いについて、また状況別の提出方法についても解説します。この記事を読めば、死亡診断書についての理解が深まります。
遠方からでも大歓迎!
遺品整理、生前整理ならお任せください。
すぐに駆けつけます!
- 365日年中無休で対応
- 最短30分で駆けつけ見積もり
- 鍵預かり、遠方対応可能
- ご見積もり後のキャンセル無料
目次
死亡診断書とは
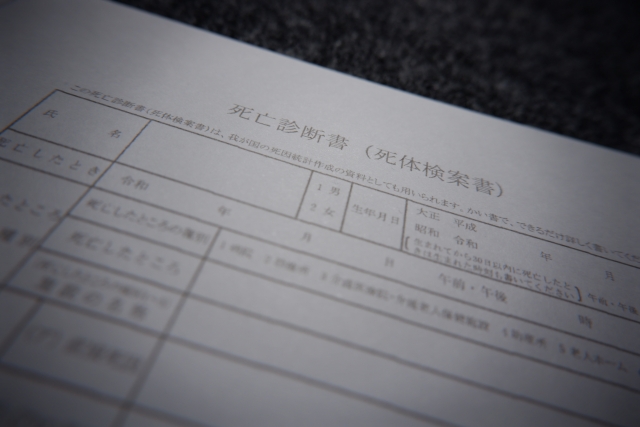
死亡診断書とは、人が亡くなったときに死亡届と合わせて市区町村役場に提出する書類です。死亡診断書がないと、葬儀や火葬、埋葬の許可がでないため、必要になる書類のひとつです。
死亡届、死亡診断書の提出がなされないと法的には生存しているとみなされ、課税や年金の支給なども継続、また相続などの手続きも行えません。
死亡診断書は亡くなった人の死亡を医学的・法律的に証明するものであり、死亡に至るまでの過程をできるだけ詳細に記入しなくてはなりません。
死亡を確認できるのは医師のみであることから、死亡診断書の記入も医師が行います。
死体検案書との違い
死亡診断書と死亡検案書には明確な違いがあります。死亡診断書が発行されるときと死体検案書が発行されるときの違いは以下の通りです。
| 死亡診断書 | ・医師が診察していた患者が、診療していた病気やケガに関連して亡くなった場合 |
| 死体検案書 | ・医師の診察を受けていなかった人が、病気やケガなどで亡くなった場合 ・医師の診療は受けていたが、診療内容とは別の原因で亡くなった場合 ・ご遺体に何らかの異常があると認められる場合 |
死亡診断書と死体検案書の大きな違いは、死因や死亡時刻を特定するための「検視」が必要かどうかです。
医師による診察を受けていない、または受けていた診察とは別の原因で亡くなった場合や、ご遺体になんらかの異常が認められる場合、医師による検視が行われます。
検視によって死因や死亡時刻を特定したのち、記入、発行されるのが死体検案書です。
生前から診察を受けていた方が、その診察を受けていた病気やケガに関連して亡くなった場合は検視の必要はなく、医師により死亡診断書が発行されます。
死亡診断書と死体検案書の用紙は同じもので、表題は「死亡診断書(死体検案書)」となっています。従って記入する内容そのものに違いはありません。
死亡証明書との違い
死亡証明書とは、死亡届が提出されたことを証明する書類です。そのため死亡届の写しとも呼ばれています。
死亡届をコピーした下部に、「日付印」、「市長印」、「公印」を押印したものがそれにあたり、原則として非公開とされています。
ただし、以下のような場合において、公開・発行されます。
- 遺族年金の請求
- 労働災害保険の請求
- 郵便簡易保険の死亡保険金請求
必要に応じて発行手続きをしましょう。
死亡診断書の中身
死亡診断書への記入は医師が行います。死亡診断書の記入項目は以下のようになっています。
死亡した方の氏名、性別。生年月日
死亡した日時
死亡した場所
死亡の原因
死亡の種類(病死および自然死、外因死、不詳の死)
外因死の追加事項(発生した場所や状況)
生後1年未満で病死した場合の追加事項
そのほか特に付言すべき事柄
診断年月日、病院名、医師の氏名
外因死とは、交通事故、転倒、溺水、煙、火災及び火焔による傷害、窒息、中毒、その他を指す不慮のものと、自殺、他殺などを含む不詳の外因死があります。外因死の場合、その傷害が発生した日時や場所などを、特筆事項として記入します。
「誰が」、「いつ」、「どのような原因で」死亡するに至ったかを詳細に記入するのが死亡診断書です。
死亡証明書を取得するタイミング
死亡証明書は、死亡届を提出、受理されたことを証明する書類なので、取得できるのは死亡届の提出後です。必要になったタイミングで取得してください。
死亡証明書は原則として非公開ですが、必要に応じて取得できます。
- 遺族年金を請求するとき
- 労働災害保険を請求するとき
- 郵便局簡易保険を請求するとき
遺族年金の受給は配偶者が亡くなったときから始まります。そのためできるだけ早く取得し、手続きをしてください。
遺族年金の申請期間は5年となっており、たとえ受け取れる要件を満たしている場合でも手続きをしないままだと時効になってしまうため、忘れずに手続きをしましょう。
また死亡証明書を取得する時期によって請求先が変わるため、確認しておきましょう。
| 死亡届を提出した場所 | 請求先 |
|---|---|
| 本籍地のある市区町村役場 | 1ヶ月以内…死亡届を提出した市区町村役場 1ヶ月以降…故人の本籍地を管轄する法務局 |
| 本籍地以外の市区町村役場 | 1年以内…死亡届を提出した市区町村役場 1年以降…故人の本籍地を管轄する法務局 |
死亡届を提出したのが、故人の本籍地のある市区町村役場である場合、死亡届を提出してから約1ヶ月以内であれば死亡届を提出した市区町村役場で受け取れます。
1ヶ月以上経過すると、死亡届は故人の本籍地を管轄する法務局に移されます。1ヶ月を過ぎている場合は、法務局に請求してください。
また故人の本籍地以外の市区町村役場に死亡届を提出した場合、1年以内であれば市区町村で死亡証明書を受け取れます。1年以上過ぎている場合は、法務局に請求します。
死亡証明書の保存期間は市区町村役場によって異なるため、詳しい時期は役所に確認してください。また法務局に移管された後の保存期間は27年間です。
関連記事:「死亡後の手続きとは?家族が亡くなった後ににすべき手続きと期限を徹底解説」
死亡診断書の発行手続き方法
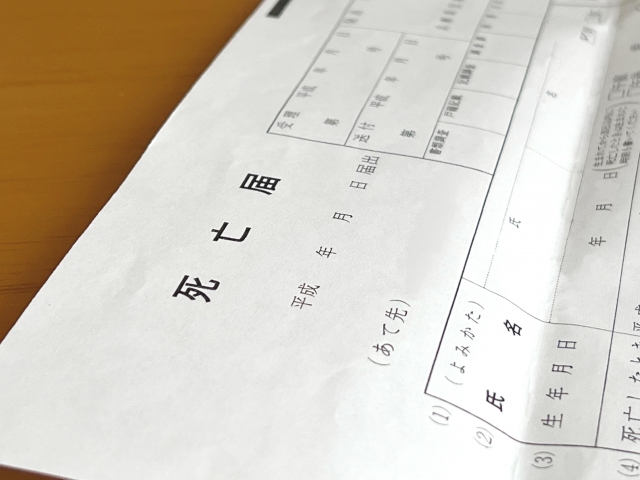
死亡診断書か死体検案書のどちらが発行されるかは死亡した状況によって異なりますが、いずれの場合も医師によって記入され、発行されます。ここでは、次の状況においての発行方法を解説します。
- 自宅でなくなった場合
- 病院で亡くなった場合
- 事故でなくなった場合
それぞれの状況と発行手続きについて解説します。
自宅で亡くなった場合
自宅でなくなった場合、亡くなった方が病院で診察を受けていたかどうかで手続きが変わります。
病院で診療無しの方
病院で診療をしていない方が亡くなった場合、死亡診断書ではなく死体検案書を発行します。
なぜなら、死亡診断書を書くために必要な死因や死亡時刻が明確になっておらず、それらを特定する検視が必要だからです。
死亡診断書と死体検案書は同じ用紙であり書式も同じですが、発行に至るまでのプロセスが違います。
病院で診療有りの方
病院で診療をしていた方が亡くなった場合、主治医は死因が治療していた病気やケガに関連するものかどうかを調べ、死亡診断書を作成、発行します。
もし死因が治療中の病気やケガによるものではない場合は、死因を特定するための検視が必要です。その場合は、死体検案書が作成、発行されます。
ただし生前の診察から24時間以内に死亡した場合は、診察をせずに死亡診断書を発行する場合もあります。
病院で亡くなった場合
病院で亡くなった場合は、担当していた医師が死亡診断書を作成、発行します。手続きは必要ありません。
事故で亡くなった場合
事故に遭い病院に運ばれ、診療後に亡くなった場合は、病院で亡くなったときと同様手続きは必要なく、担当していた医師が死亡診断書を作成します。
しかし病院に運ばれる前に亡くなった、たとえば即死、自死、不自然な死の場合は、警察の指定医による検案が行われるケースも。その場合は、検案した医師により死体検案書が発行されます。
関連記事:「親が一人暮らしで亡くなった…知っておきたい対応と手続き・遺品整理について」
死亡診断書の発行にかかる費用

死亡診断書の発行にかかる費用は、発行する期間や死亡診断書か、死体検案書化によって異なります。
| 発行機関 | 費用 |
|---|---|
| 公的医療機関(大学病院など) | 3,000円~5,000円 |
| 私立病院 | 20,000円前後 |
| 介護施設 | 5,000円~10,000円 |
| 死体検案書の場合 | 30,000円~100,000円 |
死亡診断書は公的保険の適用範囲外であり、それぞれの機関が各々料金を設定しているため、費用に開きがあることがわかります。くわしく見ていきましょう。
医療機関での料金
死亡診断書は、公的保険の適用範囲外です。そのため各医療機関が独自に料金を設定しており、医療機関によって料金の開きがあります。
- 公的医療機関(大学病院など)…3,000円~5,000円
- 私立病院…20,000円前後
高いと感じることもあるでしょうが、死亡診断書は火葬や埋葬をするためになくてはならないものなので、必要な出費といえます。
介護施設での料
介護老人保健施設に入居している方が施設内で亡くなるケースでは、介護施設に勤務する医師が死亡診断書を発行することがあります。
介護施設での費用は5,000円~10,000円。医療機関と同様、施設によって開きがあります。入所の手続きをする際、書類に死亡診断書発行費用が記載されていることもあるので確認してみましょう。
死体検案書の料金
死亡診断書ではなく、死体検案書の発行費用は、おおむね30,000円~100,000円です。
死亡診断書に比べ高額になっていますが、死体検案書の場合は死因や死亡時刻を調べるという工程があるためです。
特に持病やケガがなく死亡した場合、詳しく調べなければ死因が特定できないことがあります。さらに事件性がある場合は、行政解剖や司法解剖になるケースも。そのため、死体検案書は死亡診断書に比べて高額になってしまいます。
関連記事:「孤独死の現状と防止するための対策とは?孤独死しないために家族が知っておくべきこと」
死亡診断書の提出と期限
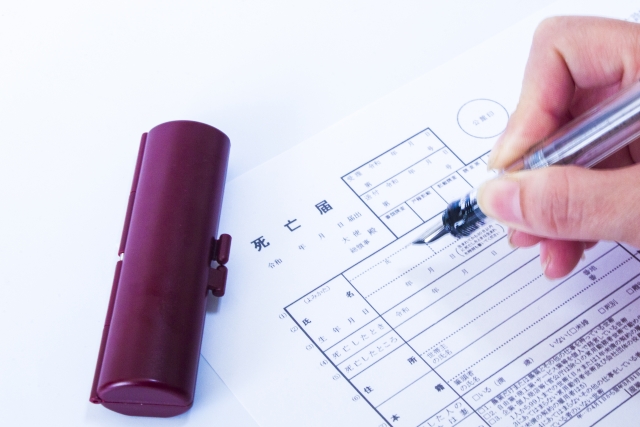
死亡診断書は死亡届と合わせて提出します。そのため提出期限は、死亡届と同じく死亡を知った日から7日以内です。ただし国外で死亡した場合は、死亡を知った日から3ヶ月以内となります。
ここでは、死亡診断書の提出に必要な書類やくわしい提出期限について解説します。
提出に必要な書類とは
死亡診断書は、死亡届と一緒に提出します。ですが左が死亡届、右が死亡診断書と1枚の用紙になっているので、実質提出するのは用紙1枚です。
死亡診断書は医師が記入しますが、死亡届は亡くなった方の家族や親族、管理人などが記入します。
・氏名
・生年月日
・死亡日時
・死亡場所
・本籍
・夫または妻の年齢
・世帯の主な仕事
・職業
届出人の情報
・故人との関係
・住所
・本籍地
・戸籍の筆頭者の氏名
・署名
・生年月日
・印鑑
故人の情報および届出人の情報を記入するので、わからないことはあらかじめ調べておくとよいでしょう。印鑑が必要なので準備します。届出人の身分証を準備しておくのも忘れないようにしましょう。
本籍地での提出と期限
死亡診断書の提出期限は死亡の事実を知ったとき、つまり死亡診断書を受け取った日から7日以内と定められています。
提出するのは、故人の死亡地、本籍地、あるいは届出人の所在地にある市町村役場で、基本的に24時間365日提出できます。窓口が閉まっているときは提出のみで受付をしていないこともありますが、提出していれば問題ありません。
届出人となれるのは、故人と以下の関係にある人です。
- 家族・親族・同居人
- 家主・地主
- 家屋管理人・土地管理人
- 後見人・保佐人・補助人・任意後見人
提出自体は、葬儀社が代行してくれることもあります。もし特別な理由なく提出が遅れると、5万円以下の過料が課せられるため、遅れないようにしましょう。
本籍地以外での提出と期限
やむを得ず本籍地以外で死亡診断書を提出することもあるでしょう。国外をのぞき、本籍地以外で死亡診断書を提出する場合でも、死亡の事実を知ってから7日以内に提出することに変わりはありません。
通常、死亡届(死亡診断書)を提出すると3日~1週間で戸籍に反映されますが、届出地と本籍地が離れている場合、書類が本籍地に届くまでに時間がかかります。
しかし、届出地と本籍地もしくは住民登録地があまりにも離れていると、各種手続きに時間がかかってしまい、反映までに2週間以上かかることも。
住民票の除籍などの手続きにも影響し、ひいては相続手続きにも影響が出る可能性があります。
よほどの理由がない限りは、本籍地か住所登録地で届け出をする方がよいでしょう。
国外で死亡した場合
国外で死亡した場合は、死亡の事実を知ってから3ヶ月以内に提出してください。
死亡診断書の提出後に必要な手続き

各種手続きのなかには、死亡診断書を提出した後に行うものも多数あります。
- 世帯主変更届
- 健康保険資格喪失届
- 年金資格喪失届
- 住民票の手続き
- 不動産の名義変更
- 葬祭費の請求
なかには期限がある手続きがあるので、きちんと確認しておきましょう。それぞれ詳しく解説します。
世帯主変更届
- 期限…世帯主の死亡を確認してから14日以内
- 届出をする場所…住民票のある市区町村役場
亡くなった方が世帯主だった場合、住民票の世帯主の欄が空欄になります。そのままにはしておけないので、世帯主の変更届を提出する必要があります。
家族でよく話し合い、世帯主を決めてください。この手続きは、世帯主が死亡してから14日以内に行います。
健康保険資格喪失届
人が亡くなると、健康保険資格喪失届を提出しますが、その期限や手続きは、加入していた保険によって違います。
- 社会保険(健康保険・厚生年金保険)
- 国民健康保険
- 後期高齢者医療保険
それぞれ見ていきましょう。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の場合
死亡した方が会社勤めをしていて社会保険に加入していた場合、手続きは会社が行います。
手続きは、管轄する年金事務所へ「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届」と「本人および扶養家族分の健康保険証」を提出します。持っている健康保険証を会社に返還しましょう。
国民健康保険の場合
国民健康保険に加入している場合は、世帯主あるいは同一世帯に属ずる人が資格喪失届を提出します。
提出先…市区町村役場
マイナンバーカードで健康保険証の利用登録をしている方もいるでしょう。マイナンバーカードは自治体で死亡届が受理された時点で自動的に失効します。そのため、健康保険証としての登録も自動的に解除されます。
後期高齢者医療保険の場合
死亡した方が後期高齢者医療保険に加入していた場合は、国民健康保険と同様、世帯主あるいは同一世帯に属する人が資格喪失届を提出します。
期限…死亡日から14日以内
提出先…市区町村役場
資格喪失届を提出する際に、保険証も返却しましょう。
年金資格喪失届
年金にも手続きが必要です。厚生年金の場合は、事業者が手続きをしますが、国民年金の場合は、家族や親族が手続きをしなくてはいけません。
手続きは、住民票がある市区町村役場、もしくは最寄りの年金事務所にて行ってください。
もし、亡くなった方の扶養に入っていた場合は、第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きも必要です。合わせて手続きするとよいでしょう。
住民票の手続き
人が亡くなると、住民票から名前が削除されます。これを証明するのが除票で、不動産や預貯金の名義変更などの手続きで使用されます。
除票は市区町村役場に死亡届(死亡診断書)を提出し、住民票からの削除が完了したら取得できます。除票の保存期間は5年間なので、必要に応じて取得しましょう。
不動産名義変更
死亡診断書を提出したら、不動産の名義変更も行いましょう。いつまでにやらなくてはならないという期限はありませんが、不動産の名義変更は相続に係わるため早めに済ませる方が良いでしょう。
不動産の名義変更には次のような書類が必要です。
- 住民票の除票または戸籍の附票
- 亡くなった方の戸籍謄本
- 不動産の固定資産評価証明書
- 不動産取得者の住民票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言書または遺産分割協議書
- 登記申請書
- 相続関係説明図(法定相続の場合)
このほかに収入印紙、場合によっては返信用封筒が必要なので、準備しておきましょう。家族を亡くしたばかりの落ち着かないときに、不動産の名義変更は負担になることもあります。難しいと感じたら、司法書士などの専門家にまかせるのもよいでしょう。
葬祭費の請求
人が亡くなると、自治体などにより葬祭費が支払われます。葬祭費の請求は、加入していた保険や状況で違います。
国民健康保険に加入していた場合
葬祭費は亡くなった方が国民健康保険(後期高齢者医療保険)に加入していた場合に支給されます。金額は自治体によって違いますが、30,000円~70,000円です。
死亡届(死亡診断書)が受理されていることが条件です。次の書類等を持って、市区町村役場に提出してください。
- 被保険者証
- 葬儀の領収書または会葬礼状
- 印鑑
- 振込先の口座番号
手続き方法は自治体によって異なるため、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。
労災保険から支給される場合
業務上、あるいは通勤中の傷病により死亡した場合、労災保険から「葬祭料」が支給されます。
葬祭料の給付金額は下記のいずれか多い金額です。
- 315,000+給付基礎日額の30日分
- 給付基礎日額の60日分
社会保険(健康保険)に加入していた場合
亡くなった方が社会保険(健康保険)に加入していた場合、下記が支給されます。
- 本人が亡くなった場合…埋葬料
- 家族が亡くなった場合…家族埋葬料
需給のための手続きは、勤務先または所轄の健康保険組合などで行います。手続きに必要な書類は次の通りです。
- 被保険者証
- 事業主の証明または死亡診断書のコピー
- 印鑑
- 振込先の口座番号
埋葬料(家族埋葬料)の金額は50,000円です。手続きは亡くなった日から2年以内に行いましょう。期間を過ぎると、支払われません。
関連記事:「親が亡くなったらすることリスト・手続き一覧まとめ。何日休むべきか目安も紹介」
死亡診断書の取得資格について

死亡診断書を取得できる人には条件があります。
取得できる人の条件
死亡診断書を取得できるのは、故人の直系親族です。直系親族とは故人の配偶者、子、父母です。
取得する際は、故人との関係を証明するために戸籍謄本のような公的書類を準備しておきましょう。
また未成年や成年被後見人の代理人がいる場合は、代理人も死亡診断書を取得できます。
委任状が必要な場合
直系親族がなんらかの事情によって死亡診断書を取得できず、他の方に取得を依頼する場合は委任状が必要です。
委任状には、次のような構成で記入しましょう。
委任者(依頼人)の氏名、住所、電話番号(連絡先)
代理人(被委任者)の氏名、住所、電話番号(連絡先)
委任する具体的な内容
委任状の有効期間
委任状を作成した日付
委任者の署名・押印
委任状は法的な効力を持っています。将来的なトラブルを避けるためにも、委任する側、される側共にコピーを保管しておきましょう。
遺品整理の相談・サポートならしあわせの遺品整理にお任せください

死亡診断書は、人が死亡したことを医学的かつ法律的に証明する書類です。医師によって記入されるもので、死亡届と合わせて市区町村役場に提出します。
死亡の事実を知ってから7日以内に提出する必要があり、遅れると50,000円以下の過料が課せられるため注意が必要です。
家族を亡くし、悲しみにくれるなかでさまざまな手続きに追われることは、心身ともに負担が大きいものです。
くわえて遺品整理も進めるとなると、その負担はより大きくなるでしょう。そんなときは「しあわせの遺品整理」にご相談ください。
遺族の心に寄り添った遺品整理はもちろん、各種手続きの相談や専門家の紹介まで、幅広く請け負っています。
「しあわせの遺品整理」は、年中無休、最短30分で現地に駆け付け、お客様のご要望にお応えします!
遺品整理士の資格を持ち、年間37967件の相談実績をもつ「しあわせの遺品整理」代表。
全国で安心して遺品整理を依頼できる世の中を目指し、人柄・費用・サービス精神を大切に遺品整理業を行っています。
遺品整理士認定番号:IS38071
- その他
遠方からでも大歓迎!
遺品整理、生前整理ならお任せください。
すぐに駆けつけます!
- 365日年中無休で対応
- 最短30分で駆けつけ見積もり
- 鍵預かり、遠方対応可能
- ご見積もり後のキャンセル無料


