四十九日までにしてはいけないこと8つ。身内が亡くなった後の過ごし方
投稿日:
更新日:
- その他
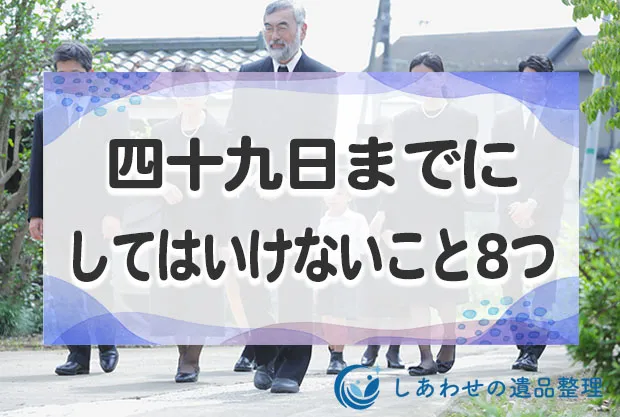
「四十九日までにしてはいけないことは?」
「四十九日までの供養って何をしたら良いんだろう?」と、不安や疑問を抱えていらっしゃる方も多いでしょう。
四十九日は仏教において故人の魂が極楽浄土へ旅立つための重要な節目とされています。
この期間は特別な意味を持ち、古来より様々な慣習や禁忌が伝えられてきました。
本記事では、四十九日にまつわる以下のポイントについて詳しく解説いたします。
・四十九日の意味と基本的な考え方
仏教における四十九日の位置づけや、故人の魂の行方、喪中・忌中との違いを明確に説明します。
・四十九日までに控えるべき8つの行為 新年の挨拶から結婚式の参加、神社参拝、旅行まで、この期間に避けるべき行為とその理由を具体的に解説します。
・四十九日までの適切な過ごし方 法要の準備や日々の供養の方法、遺品整理など、この期間にすべきことについて実践的なアドバイスを提供します。
地域や宗派によって解釈が異なる場合もありますが、故人を敬い、その冥福を祈る気持ちを大切にしながら、この特別な期間を過ごすための指針となれば幸いです。
故人との別れを受け入れ、新たな一歩を踏み出すためのお手伝いとなる情報をご提供いたします。
遺品整理業者をお探しの方へ!
- 大阪で遺品整理はこちら
- 東京で遺品整理はこちら
- 静岡で遺品整理はこちら
- 福岡で遺品整理はこちら
- 愛知で遺品整理はこちら
- 埼玉で遺品整理はこちら
- 神奈川で遺品整理はこちら
- その他の遺品整理エリアはこちら
遠方からでも大歓迎!
遺品整理、生前整理ならお任せください。
すぐに駆けつけます!
- 365日年中無休で対応
- 最短30分で駆けつけ見積もり
- 鍵預かり、遠方対応可能
- ご見積もり後のキャンセル無料
目次
そもそも四十九日とは

四十九日は日本の仏教文化における重要な法要です。
故人の冥福を祈り、あの世への旅立ちを見送るための大切な儀式として、古くから日本人の生活に根付いています。
四十九日という言葉を知っていても、具体的な意味や目的を知らない人も多いはず。
ここからは四十九日について、基本的な知識を説明します。
四十九日の意味
四十九日とは、仏教において、故人が亡くなってから49日目に行われる法要のことです。
仏教では人が亡くなると、極楽浄土に行けるかどうかを決める裁判が7日ごとに7回行われると考えられています。
最初の7日目が初七日、最後の7回目が四十九日と呼ばれます。
つまり四十九日は、故人があの世で極楽浄土へ行けるかどうかの最終的な審判を受ける日です。
そのため、遺族は四十九日まで故人が無事に成仏できるようお祈りし、丁寧に供養を行うのが日本の風習です。
四十九日法要は、故人が無事に成仏し、極楽浄土へ行くことができるよう、家族が供養と祈りの儀式として執り行うのが習わしです。
また、四十九日法要をもって忌中の期間を終えるとされており、法要後には納骨を行うのが一般的です。
四十九日の間、魂は家にいる
四十九日までの期間は、故人の魂がまだ完全にあの世に旅立っていないとされる特別な時間です。
この期間は仏教では故人が家族の暮らす家に留まっていると考えられています。
そのため、この期間は故人の魂が無事に極楽浄土へ向かえるよう、静かに見守り、供養することが大切とされています。
また四十九日を過ぎるまでは、故人の魂が住み慣れた家を離れられないという考えから、引っ越しや新しい家に移ることは避けた方が良いとされています。
四十九日の数え方
四十九日法要をいつ行うべきか、その数え方について正確に理解しておきましょう。
前提として四十九日の数え方には、いくつかのバリエーションがあります。
全国的には亡くなった日を1日目としてカウントするのが一般的です。
例えば、1月1日に亡くなった場合、2月18日が四十九日に当たります。
つまり、亡くなった日から数えて49日目が四十九日です。
ただし、地域によっては四十九日の数え方が異なり亡くなった日の前日を1日目、つまり死亡日は2日目とカウントするケースもあります。
具体的には1月1日に亡くなった方は、12月31日が1日目となり、2月17日が四十九日に該当します。
関西地方でこのような数え方をするのは、忌日の前の日にお逮夜(おたいや)という法要を行う慣習があるためです。
地域や宗派によって異なることがありますので、菩提寺の住職や葬儀社に確認するのが確実です。
喪中・忌中との違い
四十九日を理解するうえで重要なのが「喪中」と「忌中」の違いです。この二つの概念は似ているようで異なる意味を持ちます。
「喪中」とは一般的に、一周忌(いっしゅうき)の法要を終えるまでの期間のことです。
喪中とは故人を忍び、喪に服するための期間、つまり悲しみを癒すことが目的で設けられています。
悲しみの大きさや立ち直るまでの期間は故人との関係性によって違うと考えられており、故人との関係性によって喪に伏する期間が変わります。
一方、「忌中」は四十九日(しじゅうくにち)法要が終わるまでの期間です。
「忌中」は喪中のように悲しみを癒すためではなく、穢れが周囲に拡散しないように家に籠る期間を意味します。
日本では古来から死は穢れ(縁起の悪いもの)とされており、故人の家族はなるべく外部との接触を控えて、その穢れが拡散しないように配慮する風習があります。
この期間遺族は自宅に篭り、故人の冥福を祈り、飲み会などの派手な場に出席しないなど、慎み深く行動するというのが日本の考え方です。
故人との関係による忌中期間の違い
喪中と忌中の期間は、故人との関係性によって異なることも重要なポイントです。
喪中の期間は、故人との関係によって異なります。
配偶者や両親の場合は12ヶ月から13ヶ月、子供の場合は3ヶ月から12ヶ月、祖父母や兄弟姉妹の場合は3ヶ月から6ヶ月が目安とされています。
同様に、忌中の期間も故人との関係によって変わります。配偶者や両親の場合は50日間、子供や祖父母の場合は30日間、兄弟姉妹の場合は20日間が一般的な目安です。
また、数え方にも違いがあります。
喪中は一般的に一周忌までの期間と考えられている一方で忌中は、亡くなった日を含めて49日間とされています。
ただし、関西地方では亡くなった日の前日を1日目として数える場合があることも覚えておきましょう。
これらの違いを理解し、状況や地域、宗派(しゅうは)の習慣に合わせて適切(てきせつ)に対応することが大切です。
それぞれの地域や家庭の慣習を尊重しながら、故人を偲ぶ期間を大切にしましょう。
関連記事:「遺品整理は四十九日前に行うべき?親の死後いつから開始するのが良いか」
四十九日までにしてはいけないこと8つ

四十九日の期間は、故人の魂が極楽浄土へ旅立つまでの大切な時間です。
この期間中は、古来より様々な禁忌が伝えられてきました。
ここでは、四十九日までに控えるべき8つの行為について詳しく解説します
新年の挨拶
基本的に四十九日にお祝い事は厳禁なので「明けましておめでとうございます」という、お祝いの挨拶はしてはいけません。
「明けましておめでとうございます」の代わりに「本年もよろしくお願いします」「寒さ厳しき折、どうぞご自愛くださいませ」と伝えるのが良いでしょう。
新年の挨拶だけでなく年賀状の送付、新年会への参加は四十九日の期間中は控えるべきとされています。
代わりに喪中はがきを送ることで、自分が喪に服していることを周囲に知らせましょう。
また、お正月の定番であるお年玉についてもお祝いとみなされるため、好ましくはありません。
どうしても子どもたちにお金を渡したい場合は、ポチ袋ではなく封筒を使い、「お年玉」ではなく「お小遣い」として渡しましょう。
入籍・結婚式
入籍や結婚式といったお祝い事は、四十九日までは避けるのが一般的です。
これは、幸せな門出に死の穢れを持ち込まないようにするという考えに基づいています。
やむを得ず延期が難しい場合は両家や式場と相談し、特に神前式であればお祓いを受けるなどの対応をしましょう。
また、親族や友人の結婚式への参加もお祝い事に死の穢れを持ち込んではいけないという考え方から、避けるべきとされています。
七五三
七五三などの子どものお祝い事も祝いの場に穢れを持ち込むことになるため、四十九日までは避けるべきです。
子どもの健やかな成長を祝う神聖な儀式において、死の穢れは避けるべきという考え方からです。
七五三の予約をすでに入れてしまっている場合は、延期するのが良いでしょう。
神社へのお参り
神社は神聖な場所とされているため、死の穢れを持ち込むのは極力避けなければなりません。
神道の考え方では、死は「穢れ」とされており、神聖な場所である神社には穢れを持ち込まないようにするという考えから生まれた風習です。
仏教の寺院へのお参りについては特に制限はありませんが、神社への参拝は四十九日法要が済むまで控えることが望ましいでしょう。
お中元やお歳暮の贈答
お中元やお歳暮は、日頃の感謝を伝えるためのものですが、忌中は「穢れを移さない」という意味で避けた方が良いと言われています。
神道では死を穢れと捉えており、品物を贈ることで、死の穢れが伝染してしまうと考えられているからです。
なお仏教ではその考え方はしませんので、仏教徒の方へは送っても構いません。
どうしても贈る必要がある場合は、通常の熨斗(のし)ではなく、白色で無地の奉書紙か白色の短冊を使用します。
また、喜びの席を連想させる「蝶結び」ではなく、弔事用の「結び切り」の形式に則ったものを用いるなど細かなルールがあります。
なお、これらの配慮が面倒と感じる場合は、時期をずらして贈るのが良いでしょう。
旅行
旅行は遊びの側面が強いため、四十九日までは避けておくのが良いでしょう。
また、四十九日の間は故人が家に留まっているとされているので、故人があの世に旅立っていない間は家で最後の時間を一緒に過ごすという意味合いもあります。
留学や出張など、勉強や仕事のための遠出も極力避けるのがおすすめですが、やむを得ない場合は控えめに。
家族で楽しみにしていた旅行があったり、遺族が悲しみに暮れて家にいたくない場合などは、少人数から出かけても良いでしょう。
ただし、周囲から「喪中に旅行なんて」といわれる可能性もあるので、あまり周りに知らせないことをおすすめします。
なお、喪中に旅行に誘われたらお礼を伝えて、喪中だからいけないことを伝えれば理解してもらえるはずです。
飲み会
四十九日までの期間は、飲み会などの賑やかな席への出席は原則として控えることが望ましいとされています。
この期間は故人を供養しながら静かに過ごすことが大切であり、華美な席は避けたほうが良いと考えられているからです。
ただし、仕事のお付き合い程度であれば多少は許容される場合もあります。
厳密な決まりはないため、状況に応じて判断しましょう。
また、他の人に「忌中に飲み会に行くなんて」と不快に思われる可能性も考慮しましょう。
飲み会に誘われた場合は、丁寧にお礼を伝えて「喪中なので、今回は控えます」と伝えてください。
もし参加する場合は、飲みすぎて騒ぐようなことをせずに静かに過ごすように心がけましょう。可能であれば飲み会の日付をずらしたり、次の機会に参加するのがおすすめです。
引っ越しや家の新築
四十九日が過ぎるまでは、引っ越しや家の新築はお勧めしません。
これは故人の魂が四十九日を過ぎるまでは家にいると考えられているためです。
故人の魂を遺したまま新しい住まいに移ってしまうと、故人をその家に取り残してしまうことになります。
また、家という大きな物に動きがあることは、静かに過ごすべき期間にふさわしくないとされ、地域によっては怪我や不幸を招くとも考えられています。
ただし、現代では四十九日前であっても引っ越しや新居の建設を実施しても良いという考え方も広まっており、近年では喪中に関係なく引っ越しをする人も増えてきています。
転勤や就学などでやむを得ず引っ越しをする場合は、家族と話し合って気持ちに従いましょう。キャンセルが難しい場合に、無理をして取りやめる必要はありません。
故人も自分のせいで遺族が莫大なキャンセル料を払ったり、楽しみにしていた予定を延期することを望んではいないはずです。
なお、やむなく引っ越しをした場合は、住所が変わったことを喪中はがきで簡単に伝えると良いでしょう。
ただし、忌中や喪中の間は故人が亡くなったことで発生する手続きがあるので、その間に引越しや新築についての諸々をこなすのはかなり大変です。
さらに、新居を構える際の地鎮祭などのお祝いの儀式は不謹慎だといわれることもあるので、その辺りも含めて総合的に判断しましょう。
関連記事:「身内が亡くなったら葬式後の忌中と喪中でやってはいけないこととは?」
四十九日までの間の過ごし方

四十九日までの期間は、故人の魂が安らかに極楽浄土へ旅立つための大切な時間です。
この期間をどのように過ごすべきか、具体的な方法をご紹介します。
法要の準備と遺族間の連絡調整を行う
四十九日法要を滞りなく執り行うためには、余裕をもって準備を進めることが重要です。
四十九日法要の日時を決める際はまず、法要に参列してもらいたい方の予定に配慮して大体の曜日を決めましょう。
実際の四十九日の日付にこだわらず、その前後の土日にずらして集まりやすいようにするのが一般的です。
これにより、より多くの方に参列してもらって故人を極楽浄土へ送り出すことができます。
菩提寺がある場合は、早めに住職に連絡を入れて法要の依頼をしておきましょう。
早めに連絡をしないと、法要の予定自体が立たない可能性があります。
日時が決まったら参列者に連絡を取り、法要の案内と出欠確認をして人数を把握しておきます。
人数を把握できたら仕出し弁当などの手配をし、また宿泊が必要な方向けの宿の手配などもしておきましょう。
日々、供養をする
四十九日までの期間は、毎日故人のために供養をします。
この期間は故人が家に留まっているため、安心して成仏してもらうためにも、毎日以下のような供養を実施するのが好ましいです。
供養といっても何をしたら良いかわからない方のために、一般的な供養の方法を説明します。
宗派によって供養の方法が異なる場合もあるので、宗派に合わせたい場合は菩提寺等に聞くのがおすすめです。
供養の場所は「後飾り」と呼ばれる仮の祭壇で、故人の遺骨と位牌を安置しておくために使います。
後飾りは故人が亡くなった後にすぐ用意して、初七日が終わってから四十九日の法要までそのまま出しておき、その場で供養を行います。
お線香を上げる
一番一般的な供養の方法としては、毎日お線香を上げてあげることです。
お線香は故人にとって「香食」と呼ばれて、食事の代わりになると考えられています。
四十九日までは常に線香を絶やさないのが好ましいのですが、火事のリスクもあるため、人がいる間、気づいた時に炊くと良いでしょう。
なるべく長時間線香を炊いておきたいなら、渦巻状の線香を使用すると長時間火が消えないので便利です。
お水をお供えする
また、後飾りには毎日綺麗なお水をお供えしてあげてください。
綺麗なお水は故人の喉の渇きを癒す意味合いがあり、また心を清めて旅立ちを見守るという仏教的な意味合いも持っています。
灯明を灯す
さらに灯明も可能ならともしてあげてください。
灯明とは仏壇や祭壇に灯す灯火のことで、裁判を受けている故人の足元を蝋燭の火で照らしてあげる意味合いがあります。
そのため裁判が終わる四十九日までは蝋燭をつけておいてあげましょう。
なお、蝋燭をつけ続けるのは火事のリスクもあるため、蝋燭形のLEDランプなどを利用すると安全です。
お供物について
最後にお供物については、故人が好きだったお花やお菓子を添えてあげましょう。
これを供えなければならないというルールはないので、故人が喜ぶかどうかを考えてお供えしてください。
遺品を整理する(できれば)
四十九日の期間は、故人の遺品整理も少しずつ進めていくとよいでしょう。
故人の遺品は親族や親しい知人に形見分けとして渡す風習がありますが、これは四十九日頃までが目安とされています。
大切な方々に故人の思い出の品を託すことで、故人の存在が多くの人の心に生き続けることになるという考え方があるからです。
ただし、四十九日はまだ家族を亡くして悲しみもいえていない時期なので、無理をする必要はありません。
諸手続きがある場合は、遺品整理よりも手続き関係を優先して、身近な人への形見分けだけ先に済ませても良いでしょう。
遺品整理はただの私物の整理だけでなく、故人の思い出と触れ合って心を整理するための作業です。
手続きなどを済ませて気持ちが落ち着いたタイミングで、じっくりと整理をすると良いでしょう。
四十九日までの間の過ごし方や流れについてはこちらの記事で紹介しています。
遺品整理ならしあわせの遺品整理にお任せください

四十九日の法要を終え、故人の魂が無事に極楽浄土へ旅立った後、遺族の方々が取り組むべき大切な作業が遺品整理です。
これは単なる片付けではなく、故人との最後のコミュニケーションとも言える重要な儀式です。
しかし、遺品整理は感情的な負担が大きく、何から手をつければよいか迷われる方も多いでしょう。
特に四十九日までの様々な手続きや心労で疲れる時期だからこそ、専門家である遺品整理業者を頼るのもお勧めです。
「しあわせの遺品整理」では、遺品整理士の資格を持つ経験豊富なスタッフが、ご遺族の気持ちに寄り添いながら丁寧に対応いたします。
故人の思い出が詰まった品々を敬意を持って取り扱い、大切な記憶を守りながら整理のお手伝いをいたします。
また、形見分けのアドバイスや必要書類・貴重品の探索、特殊清掃が必要なケースにも迅速に対応しております。
思い出の品は大切に、不用品は適切に処分し、遺族の方々の新たな一歩を支援いたします。
遺品整理についてお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。無料見積りも行っておりますので、お電話またはお問い合わせフォームからご連絡いただければ幸いです。
遺品整理士の資格を持ち、年間37967件の相談実績をもつ「しあわせの遺品整理」代表。
全国で安心して遺品整理を依頼できる世の中を目指し、人柄・費用・サービス精神を大切に遺品整理業を行っています。
遺品整理士認定番号:IS38071
遺品整理業者をお探しの方へ!
- 千葉で遺品整理はこちら
- 兵庫で遺品整理はこちら
- 札幌で遺品整理はこちら
- 茨城で遺品整理はこちら
- 広島で遺品整理はこちら
- 京都で遺品整理はこちら
- 宮城で遺品整理はこちら
- 全国の遺品整理対応エリアはこちら
- その他
遠方からでも大歓迎!
遺品整理、生前整理ならお任せください。
すぐに駆けつけます!
- 365日年中無休で対応
- 最短30分で駆けつけ見積もり
- 鍵預かり、遠方対応可能
- ご見積もり後のキャンセル無料


