四十九日とは?意味と葬儀後から四十九日法要前後にすること・準備の方法を解説
投稿日:
更新日:
- その他

「四十九日が近づいてきたけれど、この期間に何をすべきか分からない」「故人を供養するために避けるべきことはあるの?」と迷っている方も多いのではないでしょうか。
四十九日は仏教において非常に重要な意味を持つ節目です。
故人の魂が極楽浄土へ旅立つための最終的な審判の日とされ、この期間中は様々な慣習や禁忌が古くから伝えられてきました。
本記事では、四十九日の本来の意味から、この期間の過ごし方、四十九日法要の準備と流れ、そして避けるべき行為まで、以下のポイントを中心に詳しく解説します。
・四十九日の正しい理解と宗派による違い
四十九日の意味や数え方、喪中・忌中との違い、各宗派での考え方について分かりやすく説明します。
・葬儀後から四十九日までにすべきこと
後飾り祭壇での日々の供養から法要の準備まで、時系列に沿って必要な手続きを具体的に紹介します。
・四十九日法要の進め方と必要な準備
法要当日の流れ、必要な持ち物、忌明け後の手続きなど、実践的なアドバイスを提供します。
・四十九日までに避けるべき行為
新年の挨拶から旅行、お祝い事まで、この期間に控えるべきことを詳しく解説します。
地域や宗派によって解釈が異なる場合もありますが、故人への敬意と供養の気持ちを大切に、この特別な期間を過ごすための指針となれば幸いです。
遺品整理業者をお探しの方へ!
- 大阪で遺品整理はこちら
- 東京で遺品整理はこちら
- 静岡で遺品整理はこちら
- 福岡で遺品整理はこちら
- 愛知で遺品整理はこちら
- 埼玉で遺品整理はこちら
- 神奈川で遺品整理はこちら
- その他の遺品整理エリアはこちら
遠方からでも大歓迎!
遺品整理、生前整理ならお任せください。
すぐに駆けつけます!
- 365日年中無休で対応
- 最短30分で駆けつけ見積もり
- 鍵預かり、遠方対応可能
- ご見積もり後のキャンセル無料
目次
四十九日について

四十九日は、日本の仏教文化において重要な節目です。
故人の死後、魂が新たな世界へ旅立つための大切な期間とされ、古くから様々な習わしが伝えられてきました。
ここからは四十九日の意味、数え方や宗派の違いなどについて解説します。
四十九日の意味とは
四十九日とは、故人が亡くなった日から数えて49日目に行われる法要のことを指します。
仏教の教えでは人は死後閻魔大王の裁きを受け、極楽や地獄などどこへ行くかが決まるといわれています。
この裁きは7日ごとに行われ、合計で7回、つまり終わるまでに四十九日間かかると考えられています。
各7日目には「中陰法要」と呼ばれる法事が行われ、初七日(しょなのか)、二七日(ふたなのか)と数え、最後の七七日(なななのか)が四十九日法要となります。
四十九日法要は故人の最終的な旅立ちを見送る重要な儀式であり、同時に遺族にとっては「忌明け」の日でもあります。
この日をもって故人が新たな世界で平安に過ごせるよう祈り、遺族も日常生活に戻るきっかけの日です。
喪中・忌中との違いとは
喪中と忌中は、どちらも故人を悼む期間を表す言葉ですが、その意味と期間には違いがあります。
「忌中」とは、故人が亡くなってから四十九日法要までの期間を指します。
この期間は死の穢れが強いとされ、神社への参拝や結婚式などのお祝い事を避けるのが一般的です。
また四十九日法要が済むと「忌明け」となります。
なお死を穢れと考えるのは神道の考え方であり、仏教では輪廻の一部と捉えるケースが多いです。ただ、日本は古来から神道と仏教の考え方が融合した宗教観があるので、死を穢れであり縁起が悪いと考える人はたくさんいます。
一方、「喪中」はより長い期間を指し、一般的には一周忌(故人の死後1年目の法要)までの期間とされています。
喪に服す期間として、華やかな場への参加や派手な服装を控えるなどの配慮をします。
特に近親者が亡くなった場合、喪中の期間は故人との関係によって異なり、配偶者や親の場合は1年程度、兄弟姉妹や祖父母の場合は3〜6ヶ月程度が目安とされています。
忌中が主に仏教的な意味合いが強いのに対し喪中はより社会的な慣習としての側面が強いと言えるでしょう。
正しい数え方と読み方
四十九日の読み方は「しじゅうくにち」です。
数え方については一般的には亡くなった日を1日目として数え、そこから49日目が四十九日となります。
例えば、1月1日に亡くなった場合、2月18日が四十九日に当たります。
地域によって数え方が異なる場合があるので、お住まいの地域の数え方は周囲の人に確認した方が良いかもしれません。
例えば関西地方では、亡くなった日の前日を1日目とする習慣があり、この場合は50日目が四十九日法要の日となります。
これは「逮夜(たいや)」と呼ばれる、法要前日に行う儀式の習慣に由来しています。
また、実際の法要は必ずしもちょうど49日目に行う必要はなく、前後の都合の良い日に行うケースも増えています。
ちょうど49日目が平日だと親族も集まれず、法要が開催できないことが多いためです。
そのため最近は厳密な49日というよりも、参列者が集まりやすい49日前後の土日に法要を行うのが一般的です。
宗派による考え方の違い
四十九日の考え方や儀式の内容は、仏教の宗派によって若干の違いがあります。
浄土真宗では四十九日よりも「初七日」を重視する傾向があり、四十九日法要が簡略化されることもあります。
これは阿弥陀如来の本願により、亡くなった瞬間に極楽浄土へいけるという教えに由来する考え方です。
一方で日蓮宗では、四十九日法要を「本陰」と呼び、重要視してます。
密教系の宗派である真言宗では、四十九日までの間に行われる中陰法要の際に特別な修法を行うことがあります。
曹洞宗や臨済宗などの禅宗ではシンプルな法要が中心となりますが、四十九日は重要な節目として丁寧に法要が営まれます。
このようにいずれの宗派においても、四十九日は故人の冥福を祈り、新たな旅立ちを見送るための大切な機会であることに変わりはありません。
菩提寺や担当の僧侶に相談し、各宗派の教えに沿った適切な法要を行いましょう
葬儀後から四十九日までの流れとすること

葬儀が終わってから四十九日法要までの期間は、故人を偲びながら様々な準備や手続きを行う重要な時期です。
しかし初めての四十九日法要では何をすべきかわからなくなる方も多いです。
そこでここからは、時系列に沿ってやるべきことをご紹介します。
葬儀直後〜1週間
葬儀を終えてすぐの期間は心身ともに疲れている時期ですが、初七日に向けての準備をしなければなりません。
後飾り祭壇でご供養
葬儀が終わったら、自宅に「後飾り祭壇」を設置して故人を供養します。
後飾り祭壇とは遺影や位牌、仏具、灯明などを配置し、毎日お線香やお供え物をして故人への思いを捧げるための場所です。
お供物には以下のように意味があり、内容を理解しておくと故人への供養にさらに心を込めて行えます。
- お線香…故人の食事と考えられており、四十九日までの間はできるだけ絶やさないようにするのが理想的です。現実的に常に線香を炊くのは難しいので、渦巻状の長時間燃え続ける線香を利用するのも良いでしょう。
- お水…故人の喉が渇かないように、毎日新しいお水をお供えしましょう。
- 灯明…裁判を受けている故人の足元を照らしてあげて、無事に裁判が終わって極楽へ行けるようにお祈りする意味で灯します。
なお、後飾り階段は四十九日法要が終わるまではそのまま置いておくのが一般的です。
ただし、お部屋のスペースの問題などでそれが難しい場合は、祭壇を小さめにしても問題ないでしょう。
葬儀記録を整理する
故人の葬儀では葬儀では多くの方々からご弔問を受け、香典やお花、弔電などが寄せられます。
これらの記録を整理しておくことで、後々の香典返しや挨拶回りの際に役立ちます。
参列者のリスト、香典の金額、供花や弔電を送ってくださった方々の名前などを記録しておきましょう。
また、葬儀社から渡される葬儀の写真やDVDなどは故人の思い出として、また参列者の記録の確認として役に立つので、保管しておくのがおすすめです。
お世話になった方へご挨拶を忘れずに
葬儀でお世話になった方々、特に遠方から駆けつけてくださった親族や友人には、お礼の挨拶を忘れずに。
お礼は電話やお手紙、メールなどで感謝の気持ちを伝えることが大切です。
また、葬儀社のスタッフや僧侶の方々にも改めてお礼を述べると良いでしょう。
かなり疲れている時期ではありますが、少しずつでも感謝の気持ちを伝えておくことで、今後のお付き合いも良好になるはずです。
1週間後〜四十九日前日までにすべきこと
初七日の法要を終えたら、四十九日法要に向けての準備を始めましょう。
ここからは具体的な四十九日法要の準備について解説します。
法要の日程や会場を決める
四十九日法要に向けて、会場や日程を決めていきます。
法要は必ずしも故人が亡くなった日から49日目である必要はないので、参列者が集まりやすい土日に行うケースが多いです。
参列者が少なく仏間があるなら自宅で、参列者が大勢いる場合は菩提寺、または葬儀社にスペースを借りると良いでしょう。
菩提寺や葬儀社のスペースを借りる場合は、参加者のアクセスも考えて、交通の便が良いところを選ぶと親切です。
法要の会場は早めに抑えないといっぱいになることもあるので、自宅以外で開催する場合は予約を先にしておいてください。
法要の参列者へ連絡する
法要の会場や日程が決まったら、参列してほしい方々に連絡します。
近親者や故人と親しかった方々を中心に、日時と場所、集合時間などを伝えましょう。
電話で伝えても良いですが、場所や日程に間違いがないようにメール、ハガキなどでも知らせておくと安心です。
御斎(おとき)を手配する
御斎(おとき)とは、法要の後に皆でいただくお食事のことです。
一般的に仕出し弁当を取ったり、料理店にケータリングを依頼することが多いです。
自宅の場合はお酒や飲み物などの手配も忘れずに。
食事の手配をする際は、参列者のアレルギーや子供の人数なども伝えておくと、適切な食事を選んでもらえます。
四十九日の会場がホテルや葬儀社の場合は、パッケージプランで食事を用意してもらうこともできます。
四十九日の食事は精進料理にこだわる必要はなく、故人が好んでいたものを取り入れてみるのがおすすめです。
また、故人が生前好んでいた料理屋などがある場合は、そこを食事会の会場にしても良いでしょう。
僧侶を手配する
四十九日法要を執り行う僧侶も、早めに手配しておきましょう。
菩提寺がある場合はそちらの住職に四十九日の依頼をすると、僧侶を派遣してもらえます。
特に菩提寺がない場合は葬儀社を通じて僧侶を紹介してもらうこともできるので、頼んでみましょう。
なお、僧侶の手配をする際はお布施も併せて確認しておいてください。
一般的にお布施の相場は3〜5万円ですが、菩提寺で執り行うか、自宅に派遣してもらうかによってもお布施の額が変わります。
自宅に来ていただく場合はお車代として5,000〜10,000円、会食に参加しない場合は5,000〜10,000円が一般的な相場です。
納骨法要を手配する
四十九日法要と同日に納骨を行う場合は、墓地や納骨堂へも納骨式をしたいと伝えておきましょう。
墓地の場合は管理事務所へ連絡して納骨日時を伝え、必要手続きを事前に確認しておいてください。
なお、すでにお墓があり新しく墓石に名前を入れる場合は石材店に連絡が必要です。
一般的に墓石に名前を入れるには大体1ヶ月程度かかるので、早めに連絡をしておくのがおすすめです。
引き出物を手配する
四十九日法要に参列してくださった方に渡す引き出物も、早めに準備しておきましょう。
参列者が多い場合には必要な数を揃えられない場合があるからです。
引き出物は一般的にお茶や和菓子、タオルなどを用意します。
その他、故人の趣味を反映させた引き出物も、参列者に喜ばれます。
例えば、故人がお茶を愛飲していたなら良い茶葉のセットなどを贈るのも良いでしょう。
百貨店などで依頼すれば包装や熨斗なども法要用にしてもらえるので、注文する際に伝えておきましょう。
卒塔婆を手配する
納骨式に備えて、卒塔婆も用意しておきましょう。
卒塔婆とは故人の戒名や俗名、命日を記した細長い板のことで、墓前に立てて使います。
卒塔婆はこの世とあの世の橋渡しをするとされており、卒塔婆に書かれた戒名や文言によって、故人の魂が極楽へ導かれるそうです。
卒塔婆の注文は菩提寺や葬儀社に依頼すれば作ってもらえるので、事前に依頼して作ってもらいましょう。
四十九日当日の予定
四十九日法要の当日は、以下のような流れで進行します。
事前に予定を覚えておきましょう。
四十九日法要を行う
当日は参列者への挨拶と会場への案内をし、時間になったら法要がスタートします。
僧侶が読経を行い、参列者による焼香がおこなわれるのが一般的です。
法要の進行については、菩提寺の住職や葬儀社のスタッフがしてくれるので、遺族で何かすることはほぼありません。
法要の間は故人のことを思い出しながら、安らかに眠れるようにお祈りをしましょう。
お斎(おとき)
法要の後は「お斎(おとき)」と呼ばれる会食を行います。
ここでは故人の思い出話をしたり、参列者同士で交流したりする時間です。
自宅で法要をする場合は参列者に取り皿やお箸が行き渡っているか確認したり、飲み物がたりているか目を配りましょう。
もちろん遺族も参列者と一緒に故人の思い出について語り合い、故人が明るく極楽へいけるように祈るのも忘れないでください。
葬儀社やホテルなどの会場でお食事する場合は、配膳等に気配りをする必要は無いので、参列者と思う存分故人との思い出を話し合ってくださいね。
納骨法要
四十九日と同日に納骨を行う場合は、お斎の後に墓地へ移動して納骨法要を執り行います。
僧侶による読経の後、遺骨を骨壺から取り出し、墓の中に納めるのが一般的な流れです。
納骨はお墓の中にあるカロートと呼ばれる石室へ、骨壷ごと納めます。
また、宗派によっては骨壷からお骨を出してお墓の中へお骨を納めていく場合もあります。
その場合は故人と最も近しい親族からお骨を壺から取り出して収めるのが一般的です。
四十九日明け(忌明け)
四十九日法要を終えると「忌明け」となり、様々な行事や手続きが可能になります。
香典返し
四十九日法要後、香典をいただいた方々へのお返しとして「香典返し」を行います。
香典の3分の1から2分の1程度の品物を選び、お礼状を添えて送るのがマナーです。
香典返しの期間に厳密な決まりはなく、地域や家庭の習慣によってその期間は異なります。
しかし、早めにお返しするのに越したことはないので、法要から長くとも1ヶ月以内には品物を用意して送りましょう。
形見分け
故人の遺品を親族や親しい方々に分け与える「形見分け」も、四十九日以降に行うことが多いです。
故人の想いや生前の希望を尊重しながら、形見の品を選び、故人との思い出を共有していただける方に贈ります。
もちろん遺品整理が完璧に終わっていない場合もあるので、この場では取り急ぎ思い出の品を分けるだけでも構いません。
四十九日法要当日に必要な持ち物

四十九日法要を滞りなく執り行うためには、事前の準備が大切です。ここでは、法要当日に必要な持ち物を一覧にして、詳しく解説します。
- 遺骨(お骨)
- 白木位牌
- 本位牌
- 遺影写真
- お布施
- お茶代
- 数珠
- 香典返し(引き出物)
- お供え用の花
- 喪服
- 卒塔婆(納骨を行う場合)
- 香典袋(参列者が持参するもの)
遺骨(お骨)
四十九日法要と同日に納骨を行う場合は、火葬後から大切に保管していた遺骨を持参します。納骨する際は骨壷ごと墓の納骨室(カロート)に収めるのが一般的です。
白木位牌
葬儀後から四十九日までの間、自宅で祀っていた仮の位牌です。
四十九日法要では本位牌への交換を行うため、白木位牌も持参します。
本位牌
四十九日を機に白木の仮位牌から正式な本位牌に替えるため、事前に注文しておいた本位牌を持参します。
本位牌は法要後に自宅の仏壇に安置することになります。
遺影写真
故人の遺影写真を祭壇に飾るために持っていきましょう。
一般的には、葬儀で使用したものと同じ写真を使用します。
お布施
僧侶への感謝の気持ちとして渡すお布施を用意します。
一般的には3万円から5万円程度が相場ですが、地域や寺院によって異なる場合があります。
白い封筒や慶弔両用の袋に入れ、表書きに「御布施」「御経料」などと書きます。
お茶代
菩提寺の客間を使用して会食を行う場合は、「お茶代」として5千円から1万円程度を包みます。
表書きには「御茶料」や「御礼」などと記します。
数珠
焼香の際に使用するため、忘れずに持参しましょう。家族それぞれの数珠を用意します。
香典返し(引き出物)
参列者に対するお礼として香典返し(引き出物や粗供養とも呼ばれます)を用意します。
一般的には3千円前後の品物が多く、のり、砂糖、タオルなどが定番です。
最近ではカタログギフトを選ぶ方も増えています。
お供え用の花
祭壇に供えるためのお花を用意します。
季節の花や故人が好きだった花などを選ぶと良いでしょう。菩提寺や葬儀社に事前に確認すると、適切な花の種類や量についてアドバイスをもらえます。
喪服
四十九日法要の服装は喪服が適切です。
一周忌までは喪主とその家族は略式喪服の着用を控え、正式な喪服を着用することが望ましいとされています。
卒塔婆
納骨を行う場合、卒塔婆を用意します。
卒塔婆には故人の戒名や俗名、命日が記されており、墓前に立てます。通常は菩提寺や葬儀社を通じて事前に注文します。
香典袋(参列者が持参するもの)
これは参列者が持参するものですが、香典を包む袋です。
表書きには「御霊前」や「御仏前」と書かれ、中袋には金額と贈り主の住所・氏名が記されています。
遺品整理は四十九日の前でも後でも良い

遺品整理については、必ずしも四十九日を基準にする必要はありません。
状況に応じて、遺族の心の準備ができた時に始めることが大切です。
四十九日前に遺品整理を始める場合は、故人の魂への配慮として、丁寧に扱うことを心がけましょう。
大切な書類や貴重品は早めに確認し、安全に保管することが重要です。
四十九日後に遺品整理を行えば、故人との別れを受け入れる心の準備ができてから遺品と向き合えるので、少しは気持ちの整理がつきやすいはず。
いずれの場合も、遺族同士で話し合い、互いの気持ちを尊重しながら進めることが大切です。
専門の遺品整理業者に依頼することで、感情的な負担を軽減することも検討しましょう。
四十九日までにやってはいけないこと
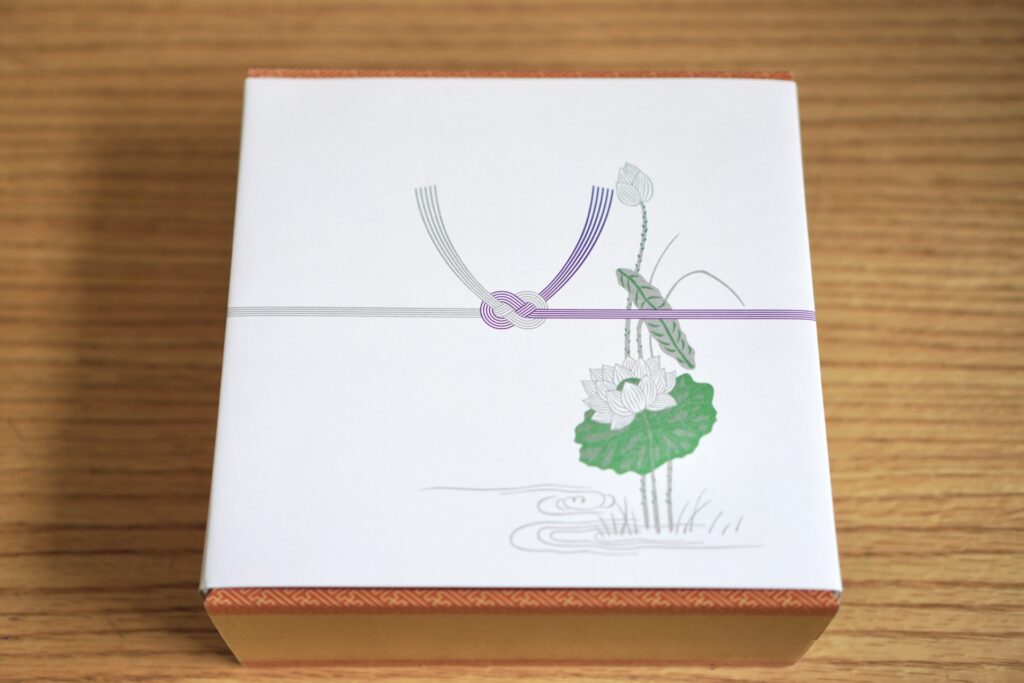
四十九日までの期間は、故人の魂があの世へ旅立つための大切な時間です。
この期間は、いくつかの禁忌があるとされていますので、念のために覚えておきましょう。
新年のあいさつ
四十九日までの期間が年末年始にかかる場合、新年の挨拶や年賀状の送付は控えるのが一般的です。
代わりに喪中はがきを送り、忌中であることを周囲に知らせましょう。
さらに新年会などの華やかな集まりへの参加も避けることが望ましいです。
お年玉を渡す場合は、ポチ袋ではなく白い封筒を使い、「お小遣い」として渡すようにしましょう。
結婚式や入籍
お祝い事である結婚式や入籍は、四十九日までは避けるのが一般的です。
これは、お祝い事に「死の穢れ」を持ち込まないという考えに基づいています。
どうしても延期できない場合は、両家や神社、式場と相談して、参加者にも理解してもらったうえで執り行いましょう。
故人の気持ちになれば、お祝い事を自分のために延期して欲しいとは思わないとは思います。
遺族の気持ち次第なところはあるので、あまり神経質になりすぎなくても良いのかもしれません。
また、他の方の結婚式への出席も控えるのが望ましいので、招待状をもらったら喪中であることを伝えてお断りしましょう。
どうしても参列したい場合は参加しても構いませんが、一応先方に喪中だけど参加しても良いかと聞くのが礼儀です。
七五三
子どものお祝い事である七五三も、四十九日までは避けるべきとされています。
これも、祝いの場に死の穢れを持ち込まないという考えからです。
可能であれば、四十九日法要が済んでから改めてお参りをするのが良いでしょう。
引っ越しや家を建てること
故人の魂は四十九日までは自宅にいると考えられているため、引っ越しや家の新築は避けた方が良いかもしれません。
これは四十九日までは故人の魂は家にとどまるという考え方に基づくものです。
この期間中に引越しをしてしまうと故人の魂が行き場を失ってしまいます。
やむを得ず引っ越しをする場合は位牌や遺影を丁寧に移動させ、新居でも供養を続けてあげましょう。
旅行
娯楽目的の旅行は、四十九日までの期間は控えるのが良いとされています。
故人の魂を見守り、冥福を祈るための期間であるため、華やかな場所への外出は避けるべきです。
また、故人がこの世にいるのは49日までですから、長期間家を留守にすると故人がひとりぼっちになってしまいます。
可能なら、四十九日までは旅行を控えて、自宅で故人の魂と過ごしてあげるのが良いでしょう。
なお、事前に計画していてキャンセルが難しいような場合は、決行しても構いません。
ただし、近所の人などで「四十九日で旅行なんて、非常識だ」というような人がいるかもしれないので、なるべく周囲の人には旅行に行くと話さない方が良いでしょう。
お中元・お歳暮を贈る
お中元やお歳暮などの贈答品も、四十九日までは控えるのが一般的です。
これは「死の穢れを移さない」という配慮からのものですが、どうしても感謝したい方に向けてのお中元やお歳暮は贈っても構いません。
その際は忌中であることを先方に伝えておくと良いでしょう。
しかし、喪中の相手からお中元やお歳暮をもらうと相手が気にする可能性もあるので、時期をずらすのがおすすめです。
どうしても贈る必要がある場合は、のし紙を白無地にするなどの配慮をしましょう。
お参り
神社へのお参りは、四十九日までは避けるべきとされています。
神道では死を「穢れ」ととらえる考え方があり、神聖な場所である神社に穢れを持ち込むことを避けるべきだと考えられているからです。
寺院への参拝については特に制限はありませんが、地域や宗派によって異なる場合もありますので、菩提寺に確認すると良いでしょう。
日常生活で必要最低限の外出は問題ありませんが、華やかな場所への外出は控えめにすることが望ましいです。
遺品整理ならしあわせの遺品整理にお任せください

四十九日の法要を終え、故人の魂が無事に極楽浄土へ旅立った後、遺族の方々が取り組むべき大切な作業が遺品整理です。
これは単なる片付けではなく、故人との最後のコミュニケーションとも言える重要な儀式です。
しかし、遺品整理は感情的な負担が大きく、何から手をつければよいか迷われる方も多いでしょう。
特に四十九日までの様々な手続きや心労で疲れている時期だからこそ、専門家のサポートを受けることも一つの選択肢です。
「しあわせの遺品整理」では、遺品整理士の資格を持つ経験豊富なスタッフが、ご遺族の気持ちに寄り添いながら丁寧に対応いたします。
故人の思い出が詰まった品々を敬意を持って取り扱い、大切な記憶を守りながら整理のお手伝いをいたします。
また、形見分けのアドバイスや必要書類・貴重品の探索、特殊清掃が必要なケースにも迅速に対応しております。
思い出の品は大切に、不用品は適切に処分し、遺族の方々の新たな一歩を支援いたします。
遺品整理についてお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。
無料見積りも行っておりますので、お電話またはお問い合わせフォームからご連絡いただければ幸いです。
遺品整理士の資格を持ち、年間37967件の相談実績をもつ「しあわせの遺品整理」代表。
全国で安心して遺品整理を依頼できる世の中を目指し、人柄・費用・サービス精神を大切に遺品整理業を行っています。
遺品整理士認定番号:IS38071
遺品整理業者をお探しの方へ!
- 千葉で遺品整理はこちら
- 兵庫で遺品整理はこちら
- 札幌で遺品整理はこちら
- 茨城で遺品整理はこちら
- 広島で遺品整理はこちら
- 京都で遺品整理はこちら
- 宮城で遺品整理はこちら
- 全国の遺品整理対応エリアはこちら
- その他
遠方からでも大歓迎!
遺品整理、生前整理ならお任せください。
すぐに駆けつけます!
- 365日年中無休で対応
- 最短30分で駆けつけ見積もり
- 鍵預かり、遠方対応可能
- ご見積もり後のキャンセル無料


