生前整理とは?いつから始める?メリット・デメリットと進め方の5ステップを紹介!
投稿日:
更新日:
- 生前整理
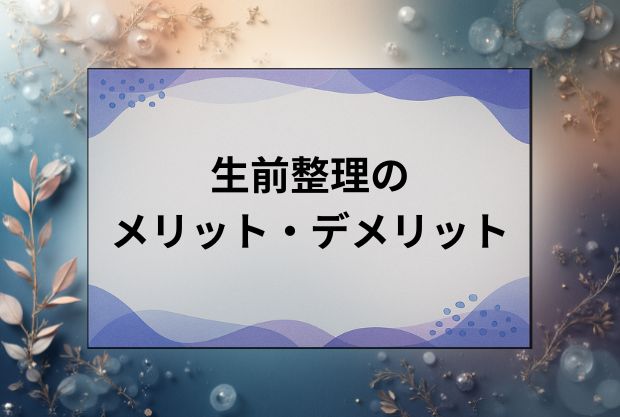
生前整理という言葉を耳にする機会が増えてきました。
しかし、「まだ早いのでは」「縁起が悪い」と感じて、なかなか踏み出せない方も多いのではないでしょうか。実は生前整理は、人生の終わりのための準備ではなく、これからの暮らしをより豊かにするための大切な取り組みです。
本記事では、生前整理の本質的な意味から具体的な進め方まで、誰もが実践できる形でご紹介していきます。一歩踏み出すことで、きっと新しい発見や気づきが待っているはずです。
この記事では、以下のような内容をまとめています。
・生前整理とは何か?
生前整理は遺される遺族のためにするもの、縁起が悪いと感じている人も多いですが、実は自分自身のための片付けなのです。この章では、生前整理を前向きに捉えていただくための内容を解説しています。
・生前整理をするメリットとデメリットについて
生前整理のメリットとデメリットを、包み隠さずお伝えします。しっかり読んで、今自分が生前整理と向き合うべきなのかを考える参考にしてください。
・生前整理はいつから始めるべきなのか
生前整理を始める時期に明確な決まりはありませんが、50代から始めるほうが多いです。いつ始めても早すぎることはなく、遅すぎることもありませんので、ご自身のタイミングを考えてみましょう。
・生前整理の具体的なステップ
生前整理といっても何をすれば良いかわからない方も多いでしょう。
具体的に生前整理を進めるために必要なステップを、生前整理業者の目線から解説します。
・生前整理における4つの重要なポイント
生前整理をする際の4つのポイントをご紹介します。心の持ち方や進め方、整理の方法についてのコツに触れているので、ぜひ参考にしてください。
・生前整理業者を活用する方法
生前整理を自分だけで行うのが不安なら、生前整理業者を活用しましょう。
生前整理業者に依頼できることや費用相場、業者選びなどについてまとめています。
いますぐ生前整理業者をお探しの方へ
遠方からでも大歓迎!
遺品整理、生前整理ならお任せください。
すぐに駆けつけます!
- 365日年中無休で対応
- 最短30分で駆けつけ見積もり
- 鍵預かり、遠方対応可能
- ご見積もり後のキャンセル無料
目次
生前整理について詳しく知ろう

エンディングノート、終活など、メディアでも盛んに取り上げられている「生前整理」ですが、具体的に何をするかイメージがついていない方もいるのではないでしょうか。
また、生前整理の意義が理解できず手がつけられない方もいるでしょう。
特に、近年では単身世帯の増加や家族形態の変化により、「モノ」の整理や引き継ぎ方に悩む方が増えています。また、デジタル化の進展により、スマートフォンやパソコンの中の写真や情報の整理など、新たな課題も生まれており対処法がわからない場合もあるでしょう。
ここからは、生前整理とはどんな意義があるのか、遺品整理や老前整理との違いについて解説します。
生前整理:自分のための片付け
まず生前整理とは元気なうちに身の回りの品物を処分したり、整頓したりして、万が一のことがあった際に身内が困らないようにするための片付けです。
こう聞くとまるで、死ぬための準備をしているみたいと感じて嫌悪感を覚える方もいるでしょう。
しかし、生前整理はあなたのための片付けでもあります。もしも体が動かなくなって、家族があなたの身の回りのものを勝手に捨てたらどんな気持ちになるでしょうか?
生前整理はあなたのために、自分自身の持ち物を整理するための機会です。
また、生前整理は老後に備えてこれまでに溜め込んだ不要なものを整理し、身軽になることで、これからの人生を前向きに過ごすための準備という意味も持っています。
今一度あなたが大切にしてきたもの、思い出を見返すことで今後の人生で大切にするものを選び抜いて、本当に大切にすべきものを愛しながら過ごすことができるでしょう。
遺品整理との違い:誰のためにいつするのか
遺品整理と生前整理は言葉自体は似ていますが、全く意味が違います。まず遺品整理は誰かが亡くなった後に、その方が持っていたものや遺産、遺品を整理することです。
遺品整理は故人にはできないので、遺族の方がおこないます。
生前整理は体が元気なうちに、その人自身が持ち物を整理することを意味します。持ち物を整理するのはご自身なので、自分の価値観や意思を反映させた整理が可能です。
例えば形見分けでトラブルにならないように、宝石は娘に、車は息子になどと生前整理をきっかけに遺言書を作成することもできます。
まとめると遺品整理は誰かが亡くなった後、その遺族が実施するものであり、生前整理は本人が元気な時に行うものです。
老前整理との違い:年齢は関係ない
老前整理とは老いる前に身の回りを整理することを意味します。老いるの基準に明確な定義はなく、いつ始めても構いませんが、50代で整理を始める方が多いです。
これは50代のまだ体力があるうちに整理を始めた方が身体的にも楽であること、また定年を迎える60代前に整理をすることで老後のプランを考えやすいからです。
もちろん老前整理はいつ始めても間違いではないので、極端な話ですが40代で始めても良いのです。
遺品整理と生前整理の違いはこちらの記事で紹介しています。
生前整理を行うメリット・デメリット

生前整理に腰が重い方は「なんとなく面倒、縁起が悪い」と感じている方が多いでしょう。
より論理的に生前整理を考えるために、メリットとデメリットを比べてみてください。
メリット
まず生前整理のメリットを紹介します。
大切な人への負担を減らせる
生前整理の最大のメリットは、将来、家族や親族の負担を大幅に減らせることです。
特に突然の事態が起きた時、家族は精神的なショックを受けている中で様々な手続きに追われます。
その際に事前に大切なものをまとめておいたり、遺産の配分について指示があれば、遺族の負担は大幅に減るでしょう。
人生を前向きに見直すチャンス
生前整理は物を片付けるだけでなく、人生を振り返る貴重な機会となります。
長年集めてきた思い出の品々と向き合うことでこれまでの人生を整理し、これからの生き方を考えるきっかけになります。
断捨離によって心身ともに軽やかになり、新しいことにチャレンジする意欲が湧いてくる方も多いです。
相続トラブルを未然に防ぐ
生前整理では財産の整理も重要な要素です。
遺産分割で揉めるケースの多くは、故人の意思が不明確だったことが原因です。
生前整理の過程で遺言書を作成し、大切な品々の行き先を決めておくことで、相続トラブルを防ぐことができます。
断捨離が運気上昇につながる可能性も
物が多すぎる環境は気の流れを滞らせると言われています。
生前整理で不要な物を手放すことで、新しい気の流れが生まれ、運気アップにつながる可能性があります。
また、整理された清潔な空間で暮らすことは、心身の健康にもよい影響を与えます。
すっきりした部屋で暮らす中で活力が湧いてきて、より行動的なあなたになれるかもしれません。
断捨離して出たゴミの処分についてはこちらの記事で紹介しています。
デメリット
次は生前整理をおこなうデメリットについても解説しますので、メリットと比較しておきましょう。
時間と労力がかかる場合も
生前整理は思い出の品々と向き合いながら整理する必要があるため、かなりの時間と労力を要します。
特に長年住んだ家の場合、物が多く、一度には片付けられない量になっていることも。判断に迷う品々も多いため、心理的な負担も大きくなります。
たとえば、着物や食器などの思い出の品は、「捨てるべきか残すべきか」の判断に時間がかかります。また、古い書類や写真は一枚一枚確認する必要があり、予想以上に時間を要するでしょう。
体力的な面でも、重い家具の移動や高所の作業など、身体的負担が大きい作業が含まれるためついつい面倒になるかもしれません。
処分費用が嵩む場合がある
生前整理では不要になった家具や電化製品の処分が必要になります。粗大ごみの処分には費用がかかり、品物の量が多いと予想以上の出費になることがあります。
また、遺品整理業者に依頼する場合は、作業費用も必要です。
例えば、タンスや食器棚などの大型家具は1点あたり1,000円から3,000円程度の処分費用が必要です。
また、エアコンなどの家電製品は、リサイクル料金に加えて収集運搬料金も必要となり、合計で1万円前後かかることもあります。
さらに、貴重品や骨董品の査定・鑑定にも専門家への依頼費用が発生する可能性も。
物の処分にかかる費用だけでなく、家族との意見の相違による精神的な負担も考えられます。生前整理を進める中で、物の処分について家族と意見が分かれることがあります。
ただし生前整理の強みはあなたの意思で決められること!遺品整理と違って遺族の意思だけで進まないので、きちんと話し合って整理の方針を決めましょう。
生前整理はいつから始めるのがベストか

生前整理を始める時期はいつが適切なのかという質問をいただくこともありますが、実は時期は特に決まっているわけではありません。
しかし、思い立ったら「いまはじめる」のがおすすめです。
今すぐ始めるのがおすすめ
生前整理は早く始めるほど良いという特徴があります。
なぜなら、体力のあるうちに少しずつ進められるからです。年齢を重ねてから始めると、体力的な負担が大きくなり、思うように進まないことも。
また、早めに始めることで、整理のペースを自分で決められます。たとえば50代から始める方の場合、週末に2-3時間程度の整理時間を設けることで、焦ることなく計画的に進められます。
一方、70代以降に始めると、長時間の作業が難しくなり、家族の手助けが必要になることも多くなります。また、判断力が低下することで、物の処分の決断が難しくなるケースもあるでしょう。
ライフステージの変化・区切りに合わせて始める
生前整理は、定年退職や子どもの独立など、人生の節目に合わせて始めるのも効果的です。環境の変化に伴い、必要なものも変わってくるため、自然な形で整理を進められます。
引っ越しや家の建て替えなども、生前整理を始めるきっかけとして最適です。
たとえば、子どもが独立する時期は子ども部屋の片付けを機に、家全体の整理を始めるのに適しています。使わなくなった学習机や本棚、子どもの成長記録など、これまで保管してきた思い出の品を整理する良い機会です。
また、定年退職後は時間に余裕ができ、仕事関連の書類や道具の整理から始められます。
さらに、老後の住まい方を考え始める60代前後も、生前整理の重要なタイミングとなります。
たとえば、将来的な住み替えを視野に入れている場合、広い家から必要最小限の荷物で暮らせる環境への移行を考えて、段階的に整理を進めることができるでしょう。
関連記事:「生前整理を30代から始める人が続出!メリットや理由を解説」
生前整理の進め方:具体的な5つのステップ

生前整理を具体的にどう進めたら良いのか、具体的な5つのステップを紹介します。
ステップ1:身の回りの物を整理する
生前整理は、まず目に見える物の整理から始めます。部屋ごとに以下の手順で進めていきます。
- 衣類や書類などカテゴリーごとに分類
- 「今すぐ必要」「しばらく保管」「処分」の3つに仕分け
- 処分品は「リサイクル」「売却」「廃棄」に分類
たとえば、衣類の場合、シーズンごとに分けた後、「この1年で着たか」を基準に判断すると整理しやすくなります。
書類は「要保管(保険証書など)」「要確認(古い領収書など)」「可処分(古いチラシなど)」と分けることで、迷わず仕分けできます。
ステップ2:デジタル資産を整理する
デジタル資産の整理も生前整理の重要な要素です。近年ではスマートフォンやパソコンの普及により、写真や重要書類、金融資産の多くがデジタル化されています。
デジタル資産についてもしっかり生前整理しておかなければなりません。
パソコンやスマートフォンのデータ整理では、まず写真や動画の整理から始めましょう。撮影日や場所、イベントごとにフォルダを作成し、思い出を整理するところから始めます。
特に重要な写真は、クラウドストレージにバックアップを取っておいてください。また、受け取った重要なメールや文書データも、同様に分類して保存します。
SNSアカウントの整理では、アカウントごとにログイン情報をまとめ、必要に応じて家族がアクセスできるよう準備します。特にメッセージやアルバム機能を使用している場合、それらの思い出を残すか削除するかの判断も必要です。
オンラインバンキングやその他の金融サービスについては、利用中のサービス一覧を作成し、口座番号やログイン方法を記録します。
特に二段階認証を設定している場合は、認証方法の詳細な記録が重要です。また、暗号資産(仮想通貨)を保有している場合は、ウォレットの種類や保管場所、アクセス方法を記録に残しておきましょう。
さらに電子マネーやポイントの整理も忘れずに行いましょう。交通系ICカード、商品券アプリ、ポイントカードなど、日常的に使用している電子マネーやポイントを洗い出し、残高や有効期限を確認します。
ポイントなどはできる限り現金や現物に引き換えておいた方が、万が一の際に遺族の方が困りません。
特にパスワード管理は重要です。家族が必要なときにアクセスできるよう、パスワードリストを作成し、保管場所を家族に伝えておきましょう。
ただし、セキュリティの観点から、パスワードリストは紙に記録し、金庫など安全な場所に保管することをおすすめします。デジタルデータとして保存する場合は、暗号化するなどの対策が必要です。
ステップ3:財産目録を作成する
生前整理において大切なのは、財産目録の作成です。財産目録には以下の項目を記載します。
- 預貯金口座の情報
- 不動産の権利書類
- 保険証券
- 株式や債券の情報
- ローンや借入金の状況
- 貸金庫の場所と鍵の保管場所
財産目録の作成は、単なるリスト作りではありません。将来の相続手続きをスムーズにし、家族が不利益を被らないようにするための重要な準備です。
たとえば、預貯金口座の場合、銀行名や支店名、口座番号だけでなく、主な入出金の内容(年金振込や公共料金の引き落としなど)も記録しておくと便利です。
保険証券については、生命保険、医療保険、損害保険など種類ごとに分類し、保険会社名、証券番号、保障内容、保険料の支払い方法、満期日などを記録します。
また、契約時の書類一式は保険証券と一緒に保管しておけば万が一の際に「保険証券がない」と焦ることもないでしょう。
不動産の場合、権利書類だけでなく、固定資産税の納付書や、リフォーム履歴、管理費などの支払い記録も重要です。マンションの場合は、管理組合の連絡先や管理規約なども含めておきましょう。
株式や投資信託などの金融商品は、証券会社名、口座番号、保有銘柄、購入時期、購入価格なども記録します。特に相続税の計算に必要となる情報なので、できるだけ詳しく記録することをおすすめします。
これらの情報は定期的に更新し、保管場所を家族に伝えておくことで、緊急時にも混乱を防げます。
ただし、財産目録には重要な個人情報が含まれるため、保管場所は金庫など安全な場所を選び、必要最小限の家族にのみ開示するようにしましょう。
ステップ4:エンディングノートを書く
生前整理の機会にエンディングノートを書いておく方も増えています。エンディングノートには以下の情報を記録しておきましょう。
- 医療や介護に関する希望
- 葬儀・お墓に関する希望
- 大切な思い出の品の譲渡先
- 家族や友人へのメッセージ
エンディングノートは単なる希望の記録ではなく、あなたの人生の集大成であり、大切な人々へのメッセージでもあります。記入する際は、形式にとらわれすぎず、あなたらしい言葉で想いを伝えることが大切です。
医療や介護に関する希望を記録する際は、具体的な状況を想定して記載しましょう。たとえば、延命治療を望むか望まないか、在宅介護と施設介護のどちらを希望するか、また、どのような医療機関や介護施設を希望するかなども記載します。
これらの希望は、家族と話し合いながら決めていくことで、より現実的な計画を立てることができます。
葬儀やお墓については、宗教や形式、規模、費用などの具体的な希望を記します。近年では、樹木葬や散骨など、新しい供養の形も増えているため、これらの選択肢についても家族と相談しながら検討するとよいでしょう。
また、すでに菩提寺や墓地がある場合は、その管理方法や費用についても記録しておきます。
大切な思い出の品の譲渡先を決める際は、その品物にまつわるエピソードも一緒に書き添えることをお勧めします。
たとえば、「この指輪は結婚25周年の記念に買ったもので、娘に譲りたい」「父から引き継いだ置時計は、長男に託したい」といった具合です。思い出と共に託すことで、より深い意味のある贈り物となります。
家族や友人へのメッセージは、エンディングノートの中でも特に大切な部分です。日頃は照れくさくて言えない感謝の言葉や、これまでの思い出、将来への期待や願いなど、素直な気持ちを綴りましょう。
「ありがとう」「ごめんなさい」「頑張ってね」など、シンプルな言葉でも、あなたの想いが込められていれば、必ず相手の心に届くはずです。
ステップ5:人間関係を整理する
生前整理の最後は、人間関係の整理です。これは物の整理とは異なり、より繊細で時間をかけて取り組むべき大切なプロセスです。
まず大前提として人間関係の整理の際にも、感謝の気持ちを伝えることから始めましょう。長年の付き合いの中で、なかなか言葉にできなかった感謝の気持ちを素直に伝えます。
たとえば、いつも支えてくれた友人に手紙を書いたり、世話になった恩師に電話をかけたりと、その人との関係に合わせた方法で気持ちを伝えましょう。
誤解や行き違いの解消も重要です。長年の人間関係の中では、小さな誤解や行き違いが積み重なることもあります。しかし、これらは適切な対話によって解決できることが多いものです。
たとえば、「あの時はごめんね」「実は私もあなたの気持ちを誤解していました」といった率直な言葉を交わすことで、わだかまりを解消できることがあります。
最後に、今後の付き合い方を見直すことも必要です。自分の体力や生活リズムの変化に合わせて、無理のない付き合い方を考えましょう。
たとえば、「毎週の集まりは月1回にしたい」「電話での連絡を主体にしたい」など、お互いが心地よく続けられる関係を提案します。大切なのは、相手に自分の状況を正直に伝え、理解を得ることです。
人間関係の整理は、決して関係を切ることではありません。むしろ、これまでの関係を見つめ直し、より良い形で継続していくための大切な機会なのです。焦らず、じっくりと時間をかけて取り組んでいきましょう。
生前整理の成功のコツは「生前整理の進め方を徹底解説!何から始める?注意点と成功のコツも紹介します!」をご覧ください。
生前整理のコツ【4つの重要ポイント】

最後に生前整理をスムーズに進める4つの重要なポイントを解説します。
トラブルなく生前整理を進めて身軽になるために、このポイントを意識して生前整理を進めましょう。
家族と一緒に進める
生前整理は家族と一緒に進めるのがおすすめですが、それには以下2つの理由があります。
- 物の思い出や価値について家族と共有できる
- 将来の方針について家族の意見を聞ける
生前整理を始める前に、まず家族会議を開きましょう。この会議では、なぜ生前整理を始めたいのか、どのようなペースで進めていきたいのかを共有します。
次に家族それぞれの予定も考慮しながら、具体的な作業日程を決めていくと良いでしょう。
整理作業では、思い出の品との向き合い方が重要です。たとえば、子どもの頃の写真やおもちゃを整理する際は、当時の思い出を子どもたちと語り合いながら進めることで、単なる物の整理以上の価値が生まれます。
「このおもちゃで遊んだ時の話」「この写真を撮った日の出来事」など、エピソードを共有することで、家族の絆も深まるはずです。
また、家具や骨董品など、金銭的な価値がある可能性のものは、家族で価値を確認しながら整理を進めます。場合によっては専門家に査定を依頼するかどうかも、家族で相談しながら決めていきましょう。
将来の生活についても、整理作業の合間に少しずつ話し合います。たとえば、「今の家に住み続けるのか」「どんな介護を望むのか」といった話題も、自然な流れで出てくるはずです。これらの会話を通じて、家族それぞれの考えや希望を知ることができます。
家族と一緒に整理することで、モノへの想いや価値観を共有でき、後々のトラブルを防ぐことができます。また、この機会に家族の絆を深め、将来への準備を整えることもできるのです。
前向きな気持ちで取り組む
生前整理は「終わりの準備」ではなく、「これからの人生をより豊かにするための準備」です。整理を通じて新しい発見があったり、懐かしい思い出に触れたりする機会にもなります。
整理後の快適な暮らしをイメージしながら進めることで、作業も楽しくなります。
具体的な前向きな取り組み方として、まずは整理によって実現したい暮らしを思い描きましょう。たとえば「趣味の時間を増やしたい」「家族と過ごす空間を作りたい」といった目標を立てます。
そして、整理の過程で出てきた思い出の品々を通じて、「あの時の自分は何を大切にしていたのか」「これからどんな生活を送りたいのか」を考える機会にします。
また、整理作業は新たな発見の連続です。たとえば、昔の手帳から当時の夢や目標が見つかり、もう一度挑戦してみたくなることも。
忘れていた趣味の道具が出てきて、再び始めてみようと思うかもしれません。このような発見を大切にし、これからの人生をより豊かにするヒントとして活かしていきましょう。
思い出の品との向き合い方も工夫できます。写真は現代的なアルバムに整理し直したり、デジタル化して家族で共有したり。手紙や日記は、その時の気持ちを思い出しながら読み返し、今の自分に向けてメッセージを書き添えてみるのも良いでしょう。
整理が進むにつれて、空間だけでなく心もすっきりしていきます。処分を決めた品々には「ありがとう」と感謝の気持ちを伝え、新しい持ち主の元での活用を願いながら手放します。また、残すと決めた物は、改めて大切にする気持ちを持って扱うようにしましょう。
少しずつ継続的に行う
生前整理は一度にすべてを片付けようとせず、時間をかけて少しずつ進めることが重要です。たとえば、「今日は本棚1段」「今週は衣類の冬物」など、小さな目標を立てて取り組むことで、負担なく継続できます。
整理は3ヶ月単位で大きな目標を立て、それを週単位、日単位の小さなタスクに分けて進めるのが効果的です。
たとえば、最初の3ヶ月は衣類の整理期間とし、1週目は「クローゼットの冬物」、2週目は「タンスの引き出し」といった具合に区切ります。1日の作業時間は2時間程度を目安とし、疲れすぎないよう休憩を挟みながら進めましょう。
また、カレンダーに作業予定と実績を記録していくと、進捗が目に見えて分かり、モチベーション維持にもつながります。整理の途中で新しく気づいたことがあれば、それも書き留めておくと良いでしょう。
迷ったら後回しにする勇気を持つ
整理中に悩む時は、その時点で決断を無理に下す必要はありません。「いったん保留」とし、時間を置いて考えることで、より良い判断ができます。特に思い出の品は慎重に扱いましょう。
迷った品物は、専用の「保留ボックス」を用意して一時的に保管します。ボックスには日付をメモし、3ヶ月程度時間を置いてから再度判断するようにします。
この間に、その品物について家族と相談したり、似たような思い出の品との比較を行ったりすることで、より冷静な判断が可能になります。
また、思い出の品は写真に収めたり、エピソードを書き留めたりしてから判断するのも一つの方法です。たとえば、子どもの手作り作品は写真に撮って思い出アルバムを作り、現物は厳選して残すといった方法を取れば、形を変えて大切な思い出を残すことができます。
判断に迷う場合は基準として、「最近1年以内に使用したか」「今後1年以内に使用する予定があるか」「それがなくても代用できるものがあるか」といったポイントで考えてみるのも効果的です。
ただし、これはあくまで目安です!その品物にまつわる思い出や価値観を最優先に考えましょう。
生前整理業者の活用方法

ここまで生前整理の方法を説明しましたが「手間がかかりそう」と思った方も多いでしょう。
確かに生前整理はかなり手間や時間、労力が要る作業です。
面倒でできそうにないと思うなら、生前整理業者の利用も検討してみてください。
生前整理業者が何をしてくれるのか、依頼の際のポイントを解説します。
生前整理業者のサービス内容
生前整理業者は、単なる片付けだけでなく、総合的なサポートを提供します。まず基本となるのは、大型家具の移動や搬出、不用品の仕分けといった実作業です。特に重量物の移動は怪我のリスクもあるため、プロの技術が重要になります。
また、整理の過程では様々な判断が必要になりますが、経験豊富なスタッフが価値判断のアドバイスを行います。たとえば骨董品や美術品の査定、リサイクル品としての価値判断など、専門的な知識に基づいたサポートを受けられます。
さらに、不用品の処分には様々な手続きが必要ですが、業者はこれらの手続きも代行します。粗大ごみの申請から、リサイクルショップへの搬入まで、煩雑な手続きから解放されるのは大きなメリットといえるでしょう。
業者に依頼する際の費用相場
生前整理の費用は作業の規模によって大きく異なります。1日の作業であれば5万円から15万円程度が一般的です。一方、一軒家全体の整理となると30万円〜の費用が必要になります。
この費用には作業員の人件費はもちろん、運搬車両の費用、処分場への支払いなども含まれています。一見高額に感じるかもしれませんが、安全な作業と適切な処分のための必要経費といえます。
また、貴金属や骨董品など買取可能な品がある場合は、その売却額を差し引くことで実質的な負担を減らせるので買取が可能な業者を選ぶと良いでしょう。
信頼できる業者の選び方
生前整理業者を選ぶ際は、見積もりの明確さが重要な判断基準となります。信頼できる業者は、作業内容を具体的に説明し、費用の内訳を分かりやすく提示します。特に追加料金の有無については、事前に詳しく確認することが大切です。
また、見積もり時の対応も業者選びの重要なポイントです。質問への回答が丁寧で、作業手順を具体的に説明してくれる業者は信頼できる傾向にあります。スケジュールの柔軟な調整にも応じてくれるかどうかは、実際の作業をスムーズに進める上で重要な要素となります。
実績も業者選びの大きな判断材料です。長年の実績がある業者は、様々なケースに対応してきた経験があり、予期せぬ事態にも適切に対応できる可能性が高くなります。
節約するなら部分的な利用もおすすめ
生前整理業者に全ての作業を依頼すると費用が高額になりますが、必要な部分だけを選んで依頼することも可能です。
たとえば、大型家具の移動など、一人では難しい作業だけを依頼する方法があります。また、整理の仕方についての相談だけを利用し、実作業は自分で行うという選択肢もあります。
このように業者のサービスを必要な部分だけ活用することで、予算を抑えながら安全かつ効率的に生前整理を進めることができます。
自分でできる作業は自分で行い、難しい部分は専門家に任せるというバランスの取れた進め方が、多くの方に選ばれています。
生前整理の業者の選び方とおすすめ業者はこちらの記事で紹介しています。
生前整理ならしあわせの遺品整理にお任せ!

しあわせの遺品整理では、生前整理のプロフェッショナルとして、お客様一人一人の状況に合わせたきめ細やかなサービスを提供しています。長年の経験から、物を手放すことへの不安や戸惑いをお持ちの方の気持ちを深く理解しています。
生前整理は、新しい人生のスタートラインです。しあわせの遺品整理は、その大切な一歩を、誠実な対応と確かな技術で支えます。
当社のスタッフは、お客様のペースに合わせて丁寧に生前整理作業を進めますので、「この写真はどうしよう」「この手紙は残すべきかしら」など、迷いが生じた際にはいつでも質問してください。
また、費用面でも安心してご依頼いただけるよう、明確な料金体系を設定しています。見積もり時には作業内容や料金について詳しく説明し、追加料金が発生する場合は必ず事前にご相談します。
買取可能な品物については、市場価値を考慮した適正価格で査定を行い、処分費用の軽減につなげることが可能です。
まずはお気軽にご相談ください。経験豊富なスタッフが、あなたの生前整理の不安や疑問にお答えします。
遺品整理士の資格を持ち、年間37967件の相談実績をもつ「しあわせの遺品整理」代表。
全国で安心して遺品整理を依頼できる世の中を目指し、人柄・費用・サービス精神を大切に遺品整理業を行っています。
遺品整理士認定番号:IS38071
おすすめの生前整理業者をお探しの方へ
- 生前整理
遠方からでも大歓迎!
遺品整理、生前整理ならお任せください。
すぐに駆けつけます!
- 365日年中無休で対応
- 最短30分で駆けつけ見積もり
- 鍵預かり、遠方対応可能
- ご見積もり後のキャンセル無料


